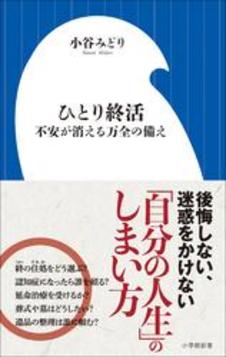「ひとり暮らしの高齢者」が要介護になったら…
認知症が進行すると、日常生活や社会生活を自力で営みにくくなるだけでなく、暴言や
暴力を振るったり、徘徊して行方不明になったり、妄想で大騒ぎしたりすることがありま
す。自分がそうなったらどうしようと心配されている方も多いでしょう。
ひとりでの生活が難しくなれば、シェアハウスやシニア向けマンション、高齢者向けの賃貸住宅や老人ホームなど、さまざまな住み替えの選択肢があります。しかし、ひとり暮らしの人は、賃貸住宅や老人ホームに入居する際に大きな壁にぶちあたります。

多くの高齢者向け賃貸住宅では、入居の際に連帯保証人と身元引受人を立てることを義務付けているからです。老人ホームのなかには、連帯保証人を2人以上必要とする施設もあります。連帯保証人は、入居者が家賃などを払えなくなった場合、代わりに支払う義務を負います。
入居者が高齢者の場合に起こる「大変なこと」
賃貸契約にあたって連帯保証人が必要なのは一般的な賃貸住宅でも同じですが、入居者が高齢者である場合は特に問題です。支払い能力がない人は連帯保証人にはなれないので、年金生活者(年金額が多ければ連帯保証人になれることもある)や無職者にはお願いできません。本人が80歳を過ぎていれば、子どもも定年退職しているかもしれないし、兄弟も同じように高齢者になっています。
配偶者や子どもがいない高齢者にとっては、連帯保証人を見つけるのはますます容易ではありません。それでは、連帯保証人がいなければ、高齢者は賃貸住宅や老人ホームに入居できないのでしょうか。
60歳以上または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の人(同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族に限る)が賃貸住宅に入居したい場合には、高齢者住宅財団の「高齢者家賃債務保証制度」が利用できます。
「保証金」の一部を助成する自治体も!
入居したい賃貸住宅がこの財団と契約していることが前提ですが、高齢者住宅の多くでこの制度が適用されています。2年間保証の場合、月額家賃と共益費の合計額の35%相当を保証料として入居者が財団に一括払いしますが、まとまったお金がないなどで保証料が払えない高齢者には、保証料の一部を助成する自治体もあります。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】