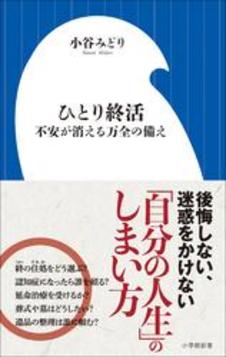要介護になっても在宅で暮らし続けるには?
認知症が進行すると、日常生活や社会生活を自力で営みにくくなるだけでなく、暴言や
暴力を振るったり、徘徊して行方不明になったり、妄想で大騒ぎしたりすることがありま
す。自分がそうなったらどうしようと心配されている方も多いでしょう。

認知症患者は高齢者全体で見れば15%程度ですが、高齢になればなるほど、認知症にかかる可能性は高くなります。厚生労働省の資料によれば、60代後半で認知症を患っている人は2.2%ですが、85歳以上では55.5%に達するそうです。85歳以上になると、2人に1人は認知症を発症していることになります。今後、長寿者の増加に伴って、2025年には認知症患者は730万人まで増加すると見込まれています。
しかし、認知症が死に直結することはありません。症状が軽いうちに適切な治療を受ければ、進行を遅らせたり、症状を改善したりできるのです。そのためには、まわりの人が早く気づくことが重要です。昨今では「もの忘れ外来」を設置する病院も増えているので、心配があれば早めに受診しておくと安心につながります。
厚生労働省は2013(平成25)年度からの「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラ
ン)」のなかで、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる環境整備を始めてきました。一例を挙げると、看護師や保健師などが家庭訪問をする「認知症初期集中支援チーム」の設置、認知症について正しく理解し、患者や家族を支援する「認知症サポーター」の拡充などです。
選択肢①:「グループホーム」での介護付き共同生活
認知症の初期ではひとり暮らしは可能ですが、道に迷う、訪問者や電話の対応に支障をきたすなどの症状が出るようになったら、どうすればよいでしょうか。それでも在宅で暮らし続けるためには、家事援助などの居宅サービスを利用する必要があります。あるいは、「グループホーム」に移り住むという選択肢も一案です。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】