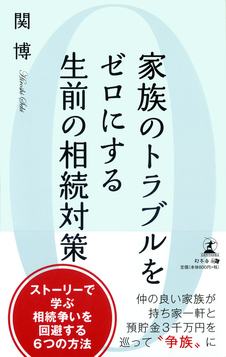「お母さん亡くなったらどうなるの?」突然の質問に…
「たぶん、母が相続すると思います」
「じゃあ、ネイルサロンもこのままね。いやよ、よそに移っちゃ」
開業してはや5年。最初はさっぱりお客が入らず、迷惑がる美千子や自分の爪ばかりいじる日々が続いた。最近はようやく常連客がつき、どうにか母娘二人の生活費を賄えるくらいにはなっている。
「でもその後、お母さんが亡くなったらどうなるの?」
「えっ? 何ですか?」
重ねて訊ねられて一美は凍りついた。
「縁起でもないことを言ってゴメンね。でも、お父さんの後にお母さんが亡くなったら、もう一度相続が起きるでしょ。その時にはこの家はどうなるのかなってこと」
そこまでは考えたことはなかった。だが常連客の言う通りだ。弟たちと自分だけが残された時には、誰が相続することになるのだろう?
一美と娘はこの家に住んでいる。ネイルサロンもようやく地域に根付いて軌道に乗り始めたところだ。家を出て新しく住まいを見つけ、また一からサロンを立ち上げることなど考えたくもない。
だが折に触れて話をする中で、弟の一太郎がこの家に愛着を持っていることは知っている。長男でもあるし、いずれ家長として継ぐのは自分だと思っているようだ。次夫は家そのものにこだわりはないようだが、事業があまりうまくいっていないのは傍目からもわかる。さらに娘の彩華がいる。亀山家最大の財産である実家を簡単に諦めるとは思えない。
自分が家を相続した上で弟たちを納得させられるような妙案はないものか。
常連客が帰るとすぐ一美は次夫に電話を入れた。事業をやっているなら、相続について相談できる税理士を知っているはず……そう考えたのだ。できることなら「長男だから」と相続で家を欲しがりそうな一太郎に対抗して共同戦線を張りたい。
■小規模宅地等の特例の非課税枠を利用する
翌々日、一美は次夫に紹介された税理士を自宅に呼んで源太郎と美千子を引き会わせた。
「大手の企業税務も扱っている事務所だから、お義父さんが相談しているところより信頼できると思うんです」
次夫と一緒にやってきた妻の彩華が税理士を紹介する。一美は前日に一度会っているが、ガッチリとした体躯にブランドものらしきスーツをまとった奥村税理士は精悍なイメージが強く、いかにもやり手に見えた。
「娘さんからご事情をうかがったのですが、相続税対策を考えておられるとか?」
奥村に訊ねられて源太郎がうなずく。