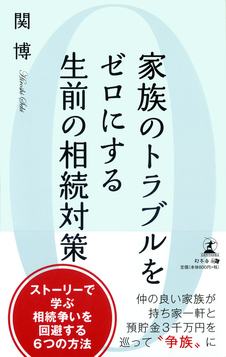息子の剣幕に父は困惑「長男だから、ねえ…」
◆日本に色濃く残る長子相続と民法
「二次相続で庭に…アパート?」一太郎に迫られて源太郎はしばし言葉を失った。
「一美姉さんだけが家を相続するというのでは、ぼくも次夫も納得できない。でもこれなら公平に分けることができるんだ」
たしかにそうだろう。さらにこれは一太郎だからできることだ。一美では、アパートを建てるための資金を借りられない。「次夫と一美姉さんには生前贈与で財産をある程度分けてあげて欲しい。それで実家を相続するとぼくとのバランスがとれると思うんだ」
「悪い案じゃないと思うわ」横で美千子がうなずく。「お庭を潰すのは悲しいけど」「そうだな」渋茶で喉を湿して、源太郎は口を開いた。
「この敷地内にサロンを開けるのなら、一美の仕事にも支障はないだろうし。ただ一美本人がどう思うか…」
「姉さんはこの家そのものに愛着はないよ。やはりぼくが家を継ぎたい。今時古いと言われるかもしれないけど、就職の時にだって長男としての義務を果たすつもりで夢を諦めたんだ。離婚をして困ったからたまたま実家に戻ってきた姉さんとは違う。そのくらいの権利を主張したって、罰は当たらないだろう」
いつもは穏やかな一太郎が気色ばむ様子に、源太郎は心中穏やかではいられなかった。次夫と彩華がたきつけたに違いない。当初は「一美と組んで…」と考えていたのが、美千子が難色を示したため一太郎につくことにしたのだろう。相続トラブルの怖さは、さんざん聞いていたが、対策を考えている段階でこんなゴタゴタが起きるなんて…。
「お前の考えはわかった。提案も検討してみる」不安を押し隠して源太郎は言った。