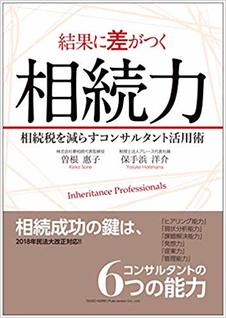相続税法で定められた評価ルール「財産評価基本通達」
その顧問税理士の間違いとは、「売買」で「相続税評価額」を用いようとしたことでした。不動産、特に土地の時価には「一物四価(いちぶつよんか)」つまり同じ土地に4つの時価が存在すると言われますが、土地の取引に対してこの4つ時価(実勢価格・公示価格・相続税評価額・固定資産税評価額)のうち、いずれの時価を使うべきかを間違えてしまったのです。各時価の特徴は、[図表1]のとおりです。
今回のお客様の件に限らず、不動産についてはどのような取引形態を取るかによって様々な税金が絡み、その際に採用すべき「時価」も変わるため間違いがとても起こりやすい分野なのです。
例えば子供などの親族間で財産を移す場合、無償いわゆる「贈与」という取引形態が用いられるケースが多いです。この「贈与」には「贈与税」がかかるのですが、その贈与税を計算する時に使う財産の「時価」には「相続税評価額」が用いられます。これは、以下のとおりに評価しておけば問題はないということを意味します。
(不動産の相続税評価額)
土地→ 路線価に基づく評価額に土地の形状などを踏まえて各種補正を加えた評価額
建物→ 固定資産税評価額(建築費のおおよそ4~6割程度)
「贈与」の場合、建物の「時価」が固定資産税評価額となっている理由は、以下のとおりです。
贈与税は相続税法の中で規定されているので、贈与税には相続税法の評価の考え方が用いられますが、この相続税法における相続財産の評価方法、すなわち「時価」の算定方法は『財産評価基本通達(以下、「財基通」)』に記載されています。この財基通で、土地の「時価」は路線価に基づく評価に各種補正を加えた価格、建物の時価は「固定資産税評価額」とされているのです[図表2]。そのため相続と贈与の場合には、建物の評価額は「固定資産税評価額」を用いて問題ありません。
同族会社とオーナー間の売買は「実勢価格」等を用いる
一方で、同族会社とオーナー間の不動産取引では「贈与」が用いられることは通常ありません。この場合、「売買」で財産を移していくことが一般的です。
この売買の際の取引価格も、「時価」で行う必要があるのですが、この売買の時の「時価」に「相続税評価額」(建物の場合は「固定資産税評価額」)を用いることは認められていません。この不動産の売買取引の際の「時価」に「相続税評価額」を使ってしまい、税務署の指摘を受けていることが多いのです。
この売買の場合には、「時価」は「実勢価格」等を用いる必要がありますので、不動産鑑定士に鑑定を依頼して金額を算定するのが原則ですが、場合によっては相続税評価額を0.8で割り戻したり、固定資産税評価額を0.7で割り戻した金額を用いたりします。
取引価格の算定を間違ってしまい、その後の税務調査で否認されることがないよう、特に不動産の法人化にあたっては、各種取引における財産評価に精通した専門家に依頼するようにしてください。
ただし、この財産評価は会計業務を専門にしている税理士さんは苦手にしているケースが多く、間違えて評価した結果として、後日、税務署から否認されるリスクが高くなりますので、法人化にあたっては、資産に関する税金(資産税)に強い税理士に依頼するのがよいでしょう。
曽根惠子
公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士
保手浜洋介
税理士法人アレース 代表社員



![[図表2]](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/1/c/500/img_1c27461e1c1f05036b253a76e88fef74197035.jpg)
![[図表2]](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/e/d/500/img_ed387b46b4d7317b52315dbcc3877108103582.jpg)