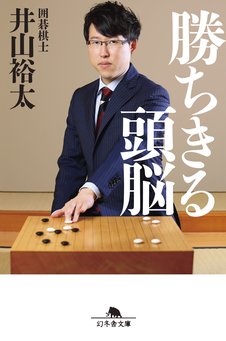「読み」は「必然の積み重ね」
◆「読み」の思考方法
自分の手番となった瞬間、まずは「直感」で候補手がいくつか浮かびます。その後、それぞれの候補手を一つずつ順番に検証していくわけですが、その検証のために必要な能力が「読み」ということになります。
つまり、「直感」で浮かんだ手を実際にそう打った場合、その後がどうなるかについて検証していくということです。その手で良いのかどうかの裏付けをとる作業と言ってもいいでしょう。
そしてファンの皆さんの興味は、この時に「プロがどれだけ読めるのか」という点に集まるわけですが、この質問に対し厳格に答えるならば「局面によります」と言うしかありません。囲碁というゲームは、かなり先まで読める局面と、一手先も読めない局面があるからです。
しかしファンの方が聞きたいのは、そうした厳格な答えではなく「読める局面なら最大どれくらい読めるのか?」でしょう。これに対してなら、僕は「百手くらい読めるケースもあります」と答えるようにしています。
そもそも、「読み」というのは「必然の積み重ね」なのです。自分がこう打てば、相手はこう打つしかない。すると自分もこう打つしかなく、相手もこう――という具合で一段落するところまでたどり着き、その出来上がった図が自分にとって良いのか悪いのかを判断する。これが基本的な「読み」の手順です。
しかし、すべての手が必然などということはまずありえず、途中のどこかで「Aという選択肢もあればBもCも」という分岐点が生じています。そしてそのAという道の先にもa、b、c、dという分岐点があり……ということで、枝葉はそれこそ無数に広がっているのです。
読みを入れるというのは、それらのすべてを検証するということですから、これはもう膨大な数になります。ですから前回の冒頭で紹介した石田芳夫先生の「ひと目千手」という言葉は、これらの枝葉すべてをひっくるめたもので、あながち誇張とも言えません(関連記事『なぜ、プロ棋士には「打つべき一手」が見えるのか?』参照)。
つまり「読み」とは「先を見通す力」なのですが、この能力には当然ながら差があります。極端な話、プロなら三〇手先まで見通すことが可能な局面だとしても、アマチュア高段者だと一〇手、アマ初段くらいの方なら六手、級位者だと三手くらいでしょうし、初心者なら「自分が打った後、相手がどこに打ってくるかもまったくわからない」ということになります。
これはどういうことかと言いますと、読みの能力が低い人ほど、自分が打ちたいと思っている手が果たして良い手なのかどうかの検証ができないということです。従って、当然ながら悪手を打つ可能性が高くなり、何手か打った後で「あ、そうだったのか!」と頭を抱えるケースが増えてしまうのです。
中国や韓国では「読みの力」を鍛錬して強い棋士を育成
囲碁には読める局面と読めない局面があることは述べましたが、やっぱり「読める局面で読める人が有利」であることは間違いありません。
なので中国や韓国では、強い棋士を養成するために若いうちから、というより若い時だからこそ、読みの力を徹底的に鍛え上げます。読める局面、つまり正解が存在する局面で正解を出せることこそが、勝てる棋士を養成するにあたっての最重要課題だとみているからです。
これまでお話ししてきたように、囲碁では「直感」が占める部分も大きいのですが、この分野はなかなか伸ばすことが困難でもあります。対して「読み」は鍛えれば鍛えるほど伸びる傾向が強いので、中国や韓国は、そうした鍛えられる部分を徹底して伸ばしていこうという方針なのです。
またこの「読み」の能力は、頭の回転の速さという瞬発力を必要としますから、「鍛えるなら若いうちに限る」と言われています。その意味で中国や韓国が若い子に徹底して詰碁をさせているのは、極めて合理的な育成方法だと言えるでしょう。
実際、僕の今の年齢(二七歳※)になってからでは、小さい頃のように伸ばすことができなくなりつつあります。だからといって鍛えることをしなければ、筋肉と一緒で衰えていく一方となってしまうので、もちろん取り組んではいます。鍛えて伸ばすというよりは、現状維持のために取り組むと言ったほうが適切でしょうか。
※2017年2月単行本刊行当時