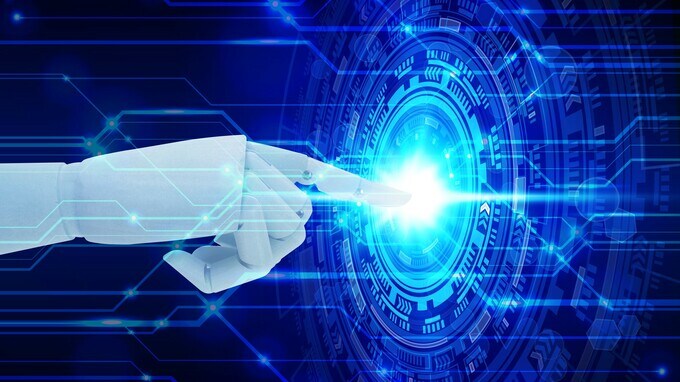国内ITの発展を阻む日本企業の体質
TRONプロジェクトの狙い
IT分野の研究開発がビジネスとして大きく展開された例が、日本にもいくつかあるのを忘れてはいけない。しかし、そこに二つ目の疑問が湧いてくる。なぜ、日本はグローバルなプラットフォームを形成することができなかったのか。
私は、幸運にももう一人の識者に取材する機会を得た。
1984年、「ウィンドウズ95」が発売される10年以上前、インターネットが普及するずっと前の時代。その年に世界に先駆けて現在でいうIoTの重要性を唱え、「どこでもコンピューティング」という言葉で、それを実現しようとした日本の研究者がいた。東京大学の坂村健先生だ。

先生は「どこでもコンピューティング」に使うべく、全技術情報をオープンとする国産OSの開発に着手する。坂村先生によるこのプロジェクトが「TRONプロジェクト」である。
TRONは3種類開発された。機器制御のためのOSで、工作機械や家電など幅広い産業用途にも利用されている「ITRON(アイトロン)」、通信機器用の「CTRON(シートロン)」。そして、コンピュータと人間の仲立ちをすると想定して考えられた「BTRON(ビートロン)」、これは今でいうPCやスマートフォンのようなグラフィカル・ユーザー・インタフェースのある機器での利用を想定したOSであった。
「ウィンドウズ」が普及する以前に、PCにも使える国産OSがあったことは今や有名な話だ。もしBTRONが海外にまで波及していたらと想像する人も多いことだろう。TRONが情報処理分野でも日本製プラットフォームの先駆けになっていたと想像するのは難しいことではない。私は坂村先生への取材を通して、これまでTRONに対して抱いていた認識を改めることになった――。
開発経緯について質問をした私に、坂村先生はこう語った。
「コンピュータの歴史を見ると、モノを制御する系統と、計算をするような情報通信の系統の2系統に分かれている。1970年ごろからマイクロチップが開発されるようになり、コンピュータが小さくなって機械のなかに組み込まれるようになった。そこでモノのなかに入れる基盤をつくろうとしたのがTRONだったんです」
その当時から坂村先生は「どこでもコンピューティング」のビジョンを描いていた。さまざまなモノにコンピュータが搭載される時代が来ると考えていた先生は、1980年代には、さまざまな開発者のさまざまなプログラムが載る基盤としてTRONを構想していたのだ。
「あらゆるモノのなかにマイコンや組み込みコンピュータが入ると思っていたから、オープンアーキテクチャの考えにならざるをえないわけですよ。プログラム自体も協力し合わないとできないし、基盤を独占してビジネスで競争しはじめると、モノ同士が連携できなくなるからです。モノの連携は非常に重要なコンセプトだと考えていたんです」
今でこそ、ITの開発環境において主流ともなったオープンアーキテクチャだが、当時の、いや現在でも日本企業が真に理解していない考え方だ。そこで思い出すのは、全国ソフトウェア協同組合連合会の安延申会長に聞いた日本語ソフト「一太郎」の失敗である。ジャストシステムの「一太郎」は、1980年代から1990年代の中盤まで絶大なシェアを誇っていた。しかし今、その地位にあるのはマイクロソフトの「ワード」だ。
一般にウィンドウズとワードの抱き合わせ販売によって一太郎が駆逐されたといわれているが、マイクロソフトの強引な販売戦略にすべての理由があるわけではない。なぜなら、それ以前に、ジャストシステムはマイクロソフトから日本語変換ソフト「ATOK」をライセンス契約してくれないかと打診されていたからだ。このときにジャストシステムは、首を縦に振らず、あくまでクローズドな環境での開発にこだわった。もしもオープンな発想ができていれば、日本語変換ソフトのスタンダードの地位を譲ることはなかっただろう。
クローズドを好む日本企業の体質では、どんなに優秀でもモノもソフトも広がりようがない。坂村先生も言う。
「プログラムやモノが連携しようというときに、いちいち企業同士が交渉して契約を交わしてとやっていたら、インフラになるような技術はできないですよ。開発そのものができないってこととほとんど同義です」
自社で自社の研究開発を疎外する日本企業――。そんな言葉が浮かんだ。
日本企業はイノベーションの起こし方を知らない
TRONを日本人は理解していたか
「オープンなプラットフォームをつくって、あらゆるモノをつなげる」というTRONプロジェクトのビジョンに対する企業や政府の無理解については、坂村先生の著書※注を読んでいても推察できる。
※注:『IoTとは何か技術革新から社会革新へ』(角川新書)
本のなかで坂村先生は日本のガバナンス意識について指摘している。ガバナンスは「統治」と簡単に翻訳されるが、「責任の所在」「誰に判断させるのかを決める権限の所在」といったニュアンスがある。おそらく日本では「何かあったときに誰がどう責任をとるか」といった思考が先行してしまったゆえに、研究開発にまつわる情報開示や共有に二の足を踏んでしまったともいえる。
坂村先生は、未だに日本の大企業がこだわる、クローズドな囲い込み戦略について厳しい意見を私に聞かせてくれた。
ハードウェアの開発製造がメインで参入障壁が高かった昔であれば技術の囲い込みにも効果はあったが、ソフトウェア開発がメインで参入障壁が低くなった今では何の効果もない。囲い込もうと特許を申請して審査を待っているうちにマーケットが制覇されてしまう時代なのだから、と。
問題はそれだけではない。坂村先生は日本企業がイノベーションを理解していないというのだ。
「誰もやったことのないことをやろうというイノベーションと、日本企業が得意なカイゼンは対極のものです。クローズドな考えになるのは、カイゼンの域を出ないから。より大きなビジョンを描けばカイゼンでは済まないし、イノベーションを起こそうとすればおのずとオープンな考えで、他社との協力が必要になるからです」
坂村先生は解決策として、テクノロジーの開発だけではなく、そのテクノロジーをどう使うかという制度設計までを議論する必要があると言う。
「シンガポールに、日本のETCに似たERPという電子料金収受システムがありますが、これを開発し導入するときに、シンガポール政府はまず法律を変えてERPを搭載しないと道路を走れないようにした。それに対して、日本ではETCを持ってない車のために有人の料金所を残すという考え方をする。この差はものすごく大きいですよ」
シンガポールのERPがいかに優れているかについては私も現地で経験した。これこそ、テクノロジーの本質を理解していない、日本のリーダーたちの決断の象徴的な例なのかもしれない。しかも、シンガポールのERPを開発したのは日本企業なのだ。その差は技術にあるわけではない。
私は、国内のメーカーがTRONプロジェクトの本質を理解し、TRONによって社会をどうするのかをきちんと議論できていれば、まったく違う現在があったのかもしれないと思わざるをえない。BTRON搭載のPCを各社が製造販売し、あるいはグローバルなプラットフォームを形成するまでに至った現在があったかもしれないからだ。
国の対応も冷淡なものだったと坂村先生はいう。ちょうど同じ時期に始まっていた第五世代コンピュータに潤沢な予算をつぎ込んだ通産省から、TRONプロジェクトへの資金援助はなかった。官僚主導ではないプロジェクトには見向きもされなかったそうだ。このときの通産省の戦略が違っていれば、また別の現在があったかもしれない。
もし、マイクロソフトやアップルが押し寄せてくるなかで、国産OSがないとIT市場のシェアもとられてしまうという未来まで想定できて、十分な危機意識につなげることができていれば…。もし、あらゆるモノがコンピュータにつながるというTRONプロジェクトの大きなビジョンを、当時から日本企業の経営者や官僚が理解していれば…。そう考えると実にもどかしい。1980年代にタイムスリップして、時代を変えられないかと空想せずにはいられない。
TRONプロジェクトをきちんと議論できなかったことは、日本の産業界の自滅にほかならないのではないかと、私は考えた。