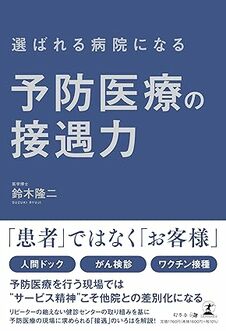まずはクレーム予防を徹底
こうした不満や訴えを防ぐたにまず大切なのは、そうした苦情が起きないように十分な対策をしておくことです。
費用についていえば、予約受付時に費用についてよく確認し、必要ならば病院と健診施設の違い、健康保険適用の有無などについて、あらかじめ説明をしておくことです。
このほか当健診センターでは、館内にゆったりとしたBGMを流し、待ち時間もリラックスした気分で過ごせるように配慮しています。待ち時間の間にも自由に利用して楽しんでもらえるように雑誌や漫画などの無料アプリも案内しています。
クレーム対応で最も大切なこと
で対応苦情や不満が収まらないときは、その受診者の訴えを「よく聴く」ことも大切です。いわゆる「傾聴」の姿勢です。
傾聴というのは医療接遇でも頻繁にいわれることですが、相手の言葉を遮ったり否定したりせず、丁寧に耳を傾け、共感的な姿勢を示すことです。こちらの事情や主張はいったん脇に置いておいて、とにかく相手の話を聴くことに徹します。
当健診センターの経験では、相手が感情的に不満をぶつけてくるような場合でも、粘り強く傾聴をしていると、それだけでクレームが自然に解消していくことがほとんどです。
不満を強く訴えていた人も、自分の話を十分に聴いてもらえたことで「理解してもらえた」「自分を尊重してもらった」という充足感が出てくるのだと思います。
なお、医療接遇としての「傾聴」の方法については、さまざまな民間企業・公的機関による講習やワークショップが行われています。そうした研修を定期的に受講し、職員の傾聴スキルを高めていくのも良い対策になります。
一人の受診者に傾聴の対応をしていると、少なくとも一人の職員の仕事の手が止まりますから、その分は周囲の職員がカバーするなどのチームの連携は必須です。
またクレームが続くときは、対応する職員を代えるのも一案です。最初の対応が男性職員なら女性職員が替わる、反対に女性職員がてこずる相手には男性職員が出ていく、というように対応する人を変えると、それだけでガラッと態度が変わって穏やかになる場合もあります。
単純に受診者と職員の“相性”ということもありますし、女性や若い職員に高圧的な態度をとる人もいれば、男性職員には当たりが強くても、女性には優しくなる人など、いろいろな人がいます。
注目のセミナー情報
【国内不動産】2月14日(土)開催
融資の限界を迎えた不動産オーナー必見
“3億円の壁”を突破し、“資産10億円”を目指す!
アパックスホームが提案する「特別提携ローン」活用戦略
【国内不動産】2月18日(水)開催