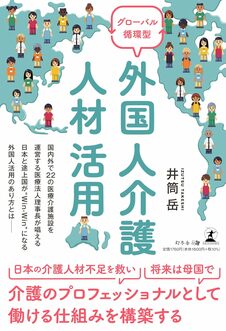食事の介助で起こりがちなトラブル
私の施設で日本人と外国人の間に認識のギャップを感じさせられたことの一つが食事です。
日本人であれば、献立表を見ればどんな料理が出てくるか想像がつきますし、和食のマナーも幼少期から自然に身につけていきます。
介護現場の仕事の一つに食事の介助があります。
食事の介助について、ひととおりのスキルを教えたあとに任せてみたところ、外国人スタッフたちはある器に盛られたおかずを平らげるまで口に運び、次にまた別の器のおかずを食べさせ続けるという食べさせ方をしていました。
日本人スタッフに仕事を教えるときに、そこまでの説明をしたことがありませんでしたが、ミャンマーの食文化を考えればそうなるのが当然でした。
ミャンマーの料理は大皿でテーブルに並びます。それに対し、白ご飯が盛られたお茶碗に、小鉢がいくつも並ぶというのが日本食の定番です。一つのおかずを一気に食べるのではなく、おかずとご飯を順番にバランスよく食べるという「三角食べ」も、外国人からすれば当たり前ではありません。
見慣れないスタイルの食事をどう食べさせればよいものか考えた結果、端から順番に食べさせることになったといいます。
また、外国人スタッフたちにとって、どの料理がどんな味なのかを見た目から想像することが難しいということがあります。そもそも使われている食材や調味料になじみがないものも多いので、甘いのか、辛いのか、酸っぱいのか、苦いのかという判断がつきません。
そのため、一目見ただけではどれがデザートなのか分からないということが起きます。
これは受け入れ前には想定していなかったことで、外国人スタッフがデザートの入っている小鉢を真っ先に手に取って食べさせようとしているのを見て、教育係が食文化を教えることの必要性に気づいたのでした。
私の施設ではこれらの経験から、試食会を行って料理を実際に味わってもらうことにしました。どんな順番で食べていくとよいかということも教えることで、食事の介助もスムーズに進むようになりました。
また、実習生たちと関わっていくなかで、味の感じ方の度合いにも違いがあることが分かってきました。ミャンマーは辛い食べ物が多いためか、ミャンマーからやって来たスタッフたちの辛いと感じる度合いが日本人とは大きく異なっていたのです。
個人差があるとはいえ、日本で普通に売られている唐辛子では少しも辛いと感じないと話す人もいるほどです。
味の感じ方の差異は目に見えない部分ではありますが、その違いを知っているのと知らないのとでは、仕事の教え方も異なってきます。
井筒 岳
社団医療法人啓愛会
理事長