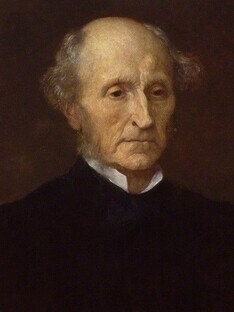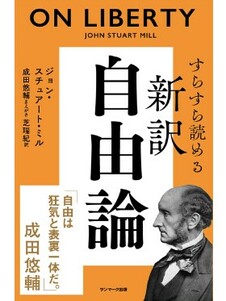国は「酒場の数」を制限できるか?
では、次の話題に移ろう。店の数を制限し、一部の人しか酒を販売できないようにするのは正当なのだろうか。これについては、正当か不当かは目的によって決まる。
警察は、人が多く集まる場所にはつねに目を光らせなければならないが、なかでもとくに注意が必要なのは酒場である。社会全体に害を及ぼすような犯罪が発生しやすい場所だからだ。
このような場所では、酒を売る権限(少なくとも、その場で飲む人に酒を売る権限)を信頼できる人だけに与えたとしても不当ではない。社会が監視できるように開店時間と閉店時間を厳密に定めることも必要だし、治安を乱したり犯罪の計画を立てたりする客が店にいるなら、店主は毅然とした態度でそういう行為をやめさせなければならない。それができない場合、その店の営業許可は取り消されても仕方がない。
社会が酒場に対して強制できるのはここまでだ。これ以上の制限を強いることは正当ではないと私は思う。たとえば、「人々が酒に誘惑される機会を減らすために酒場の数を制限する」という方法には賛同できない。一部の人のために、社会の全員に不便を強いることが正しいはずがないのだ。
この方法に賛成する人は、こう考えているのと同じだ。「労働者階級は子どものようなものだ。いつかは自由が与えられるかもしれないが、いまはまだ規律で縛って教育を与えてやらないといけない」。
「自由」を認めている国なら、こんな原則を持ち出して労働者階級を縛りつけたりはしない。また、自由の価値をじゅうぶんに理解している人なら、このような方法にはけっして賛同しないだろう。例外があるとすれば、労働者階級に完全な自由を与えるためにあらゆる努力をして、その結果「やはりこの人たちは子どもと同じように支配するしかない」と証明された場合だけだ。だが、この問題に限らず、そのような努力がなされたことがあるとは思えない。
ひとつ確かなのは、イギリスの制度が矛盾に満ちているということだ。家父長制にも似た専制的なシステムがいまだに残っている一方で、全体としては自由を重視している。そのために、道徳教育に必要な規制すら設けられずにいるのだ。
ジョン・スチュアート・ミル
政治哲学者
経済思想家
※本記事は、約165年前に出版された19世紀を代表するイギリスの政治哲学者、経済思想家ジョン・スチュアート・ミルの「自由論」を基にした新訳書籍『すらすら読める新訳 自由論』(著:ジョン・スチュアート・ミル、その他:成田悠輔、翻訳:芝瑞紀、出版社:サンマーク出版)からの抜粋です。
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】