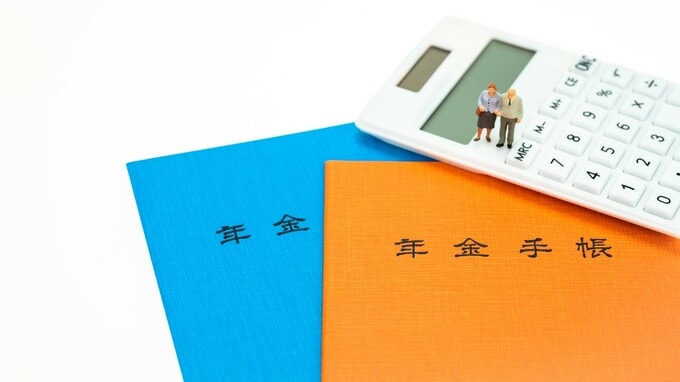必死で働き、年金の受取額を増やしても…
年金を受給できる年齢となっても就労を続ける高齢者のなかには、自分の稼ぎだけで生活できる人もいる。そういった人たちは「年金の繰下げ受給」をしているケースが多い。
年金の繰り下げ受給とは、原則として65歳から受給できる年金を、66歳~75歳までの間で繰り下げて受給することで、年金を増額して受け取れるという制度。1ヵ月繰下げるごとに年金が0.7%ずつ増額され、最大84%まで増額できる。増額された年金額はその後、一生変わらない。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることが可能だ。
たとえば平均的な元会社員夫婦の場合、75歳まで繰り下げることにより、65歳時点で「16万7,388円」だった夫の年金額は「30万7,993円」に、「10万9,165円」だった妻の年金額は「20万0,863円」に増額される。合計すれば月50万円と、およそ2倍近い金額になる。ここまで増えたなら、まさに感涙ものだろう。
だが、留意すべき点がある。収入が増えれば、税金や社会保険料も増額されるのだ。いざ受け取ったとき、天引きされた金額に驚いてしまうかもしれない。
もうひとつが「医療費負担」の増大だ。仮に、夫の年金が65歳時点で「18万円」だった場合、75歳まで繰り下げると「月33万1,200円」、年間「397万4,400円」になるが、この場合夫は「現役並みの所得者」となり、医療費負担は3割になる。
「現役並みの所得者」とは、課税所得が145万円を超えたケースを指す。課税所得は公的年金控除などの各種控除を引いたあとの金額で、収入に直すと383万円未満、月換算31万9,100円未満となる。75歳以上の医療費負担は「年金とその他の合計所得金額」が「年200万円未満」で1割負担、「年収200万~383万円未満」で2割負担、「年収383円以上」だと3割負担。繰下げ受給制度を利用することで年金収入が増え、基準を超えると、医療費の負担額も増えてしまう。
医療費の自己負担割合は、該当する年度の住民税の課税所得によって決定されるが、繰下げ受給で増額率が決まれば、その後は生涯変わらないことから、以降の課税所得が変わることは考えにくく、そのため、医療費の自己負担額も変わらない可能性が高いだろう。ちなみに、妻の課税所得がゼロの場合も、夫の課税所得が145万円を超えていれば、夫婦とも自己負担割合は3割になる。まさに「なにかの間違いでは」といいたくなる数字だ。
年齢を重ねれば、だれでも病気のリスクが上がる。せっかく無理を重ねて年金額を増やしても、夫婦で大病すれば水の泡だ。
年金額は増えるのは魅力的だが、残念ながら、それに伴う様々な負担も増えてくる。それらの点と自分の健康状態を包括的に考えて、年金受給のタイミングを決定することが重要だろう。
[参考資料]
総務省『労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果』
\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/25開催】
相続や離婚であなたの財産はどうなる?
預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策
【2/26開催】
いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?
個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質
【2/28-3/1開催】
弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】