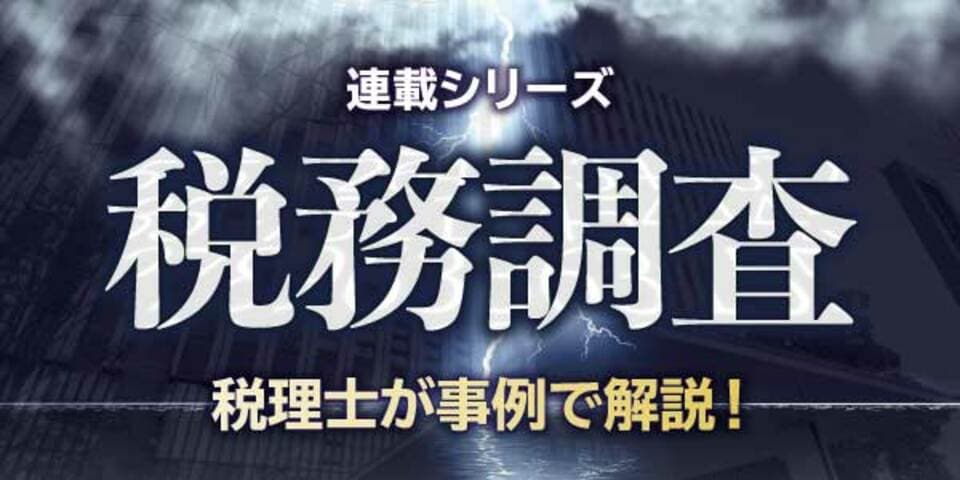税務署のお尋ねの対象となったワケ
そして、面談当日、資金を支払った通帳などいろいろ持参して説明をしていたところ、「贈与税の申告漏れがありませんか」と問われました。Aさんは驚いて、聞き返します。
「どういうことでしょうか。こちらは私の名義で貯金している通帳なのですが?」税務署の担当者はその通帳の入金元をみていたのでした。
Aさんは父親から、旅行のたび、お正月、GWなどのイベントのときに、まとまったお金を受け取っていました。そんなに派手に使うこともないAさんは、余ったお金を貯金していました。
Aさんが会社を退職して家業を手伝うようになってから恒例行事のように受け取っていたのと、父親も生活の足しにと、ちょっとしたお小遣いのつもりで渡していたので、Aさんもあまり深く考えずに受け取っていたのでした。というのも、不動産管理会社の取締役として受け取っている役員報酬は35万円と抑えめで設定されており、お小遣いにしては額が大きいけど、助かるなという気持ち程度でした。
しかし、このいびつな状態が、お尋ねの対象となってしまったのです。
役員報酬からみた年収に対しての資金の支払金額や通帳の状況など、税務署からみて少し不信感を抱く結果となってしまいました。通帳の入金についても合計してみるとここ数年でも2,000万円近くに、多い年には1年で200万円以上にもなっていました。
税務署は専用のシステムによって、過去10年間分の収入や通帳等の財産を把握することができます。このシステムは国税総合管理システム(KSK)といわれています。
国税庁や税務署では、これにより納税者情報を管理しており、そこには給与や確定申告のデータが登録されているため、そこに記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて調査します。
これらと照らし合わせて、預金の経緯や使い道を調査してくことになるのです。これまでの蓄積された過去データがあるので、申告をすべき人がしていなかったりすると税務調査の対象やお尋ねの対象になることがありますし、膨大なデータをもとに照らし合わせることで高確率で発覚します。
これにより不自然な預金の動きがあれば、一目でわかってしまうのです。結果として、Aさんは税務署の担当者と話し合いの結果、贈与税の申告漏れであることが発覚しました。
生活費や仕送りに贈与税はかからないはずでは?
通常、生活費や仕送りについては、贈与税はかかりません。しかし、これらの生活費や仕送りも一定額を定期的に送るということではなく、まとまった金額を渡し、さらにそれを預金しているなどの場合、贈与税の対象となる可能性があるのです。
Aさんの場合には、まさにその対象とされたことで贈与税の申告漏れと判断されることとなりました。贈与税の税率は比較的高めに設定されているため、直近の申告漏れでも170万円となりました。
Aさんの不動産購入というイベントについて、贈与税においては、親などから資金援助を受ける場合の非課税の制度が設けられているので、上手に利用することで、予想外の税金がかかることを防ぐことができます。
父親もAさんを想ってのことですので、予想外の結果になるとお互い残念な気持ちになってしまいます。日々の生活で見逃しそうになることでも、少し視野を広げることで気持ちよく想いを届けることができます。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
3月7日(土)~8日(日)限定配信!
日本株長期上昇トレンドの到来!
スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資
認知症となった80代賃貸不動産オーナー
家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!
『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは
遺言書があるのにやっぱり揉める!
富裕層が今すぐ備えるべき「相続の落とし穴と対策」
金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険
“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察
「これからの不動産投資」