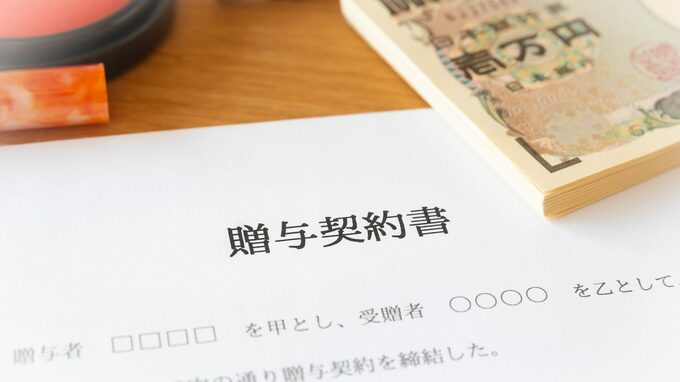損益分岐点のシミュレーション
では、具体例を用いて、損益分岐点のシミュレーションをしてみましょう。
・推定相続人:配偶者と子2人
・現時点の総資産の評価額:3億円
まず、相続税の実効税率を算出します。最初に、現時点での総資産の評価額から相続税の基礎控除額を差し引きます。相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。
このケースでは推定相続人が配偶者と子2人なので、4,800万円です。したがって、相続税の課税対象となるのは、3億円からこれを差し引いた2億5,200万円ということになります。
次に、配偶者と2人の子について、いったん、各々の「仮の相続分」を計算します。配偶者と2人の子の法定相続分は、それぞれ以下の通りです。
・配偶者:2分の1(配偶者の法定相続分)
・子1:2分の1(子の法定相続分)÷2(子の人数)=4分の1
・子2:2分の1(子の法定相続分)÷2(子の人数)=4分の1
したがって、配偶者と子2人のそれぞれの仮の相続分は以下の通りです。
・配偶者:1億2,600万円
・子1:6,300万円
・子2:6,300万円
これらに相続税の速算表([図表1]参照)を適用し、各自の仮の相続税額を算出します。
・配偶者:3,340万円
・子1:1,190万円
・子2:1,190万円
これらを合計すると、相続税の総額は5,720万円となります。したがって、相続税の実効税率は以下の通り、19.07%です。
これに対し、贈与税の実効税率を計算してみます。「贈与税の実効税率<19.07%」となるラインがどこかを計算します。
贈与税の速算表をみると、基礎控除後の課税価格が「600万円超~1,000万円以下」(税率30%、控除額90万円)または「1,000万円超~1,500万円以下」(税率40%、控除額190万円)のときに、だいたい実効税率が20%前後になりそうだと見当がつきます(ちなみに、このあたりは税理士の「勘」です)。
贈与税の額の計算式は以下の通りです。
ここで、仮に、基礎控除後の課税価格が「1,000万円超~1,500万円以下」の範囲だと見当をつけます(繰り返しますが、税理士の「勘」です)。そして、贈与額(基礎控除前の額)を「x円」(1,110万<x≦1,610万)とおくと、贈与税の額は以下の通りです。
この額が、「x円×19.07%」よりも低くなるxの値が、損益分岐点です。つまり、
となるxの値を求めればよいことになります。
これを計算すると、実効税率が19.07%未満になるのは、x=1,118万円です。したがって、この額が損益分岐点となります(なお、筆者の「勘」が当たって、ぎりぎり基礎控除後の課税価格が「1,000万円超~1,500万円以下」の範囲内でした)。
したがって、計算上は、毎年1,118万円を贈与していくことがもっとも効率が良いことになります。ただし、実際には、相続までの間に財産の額は変動するので、一応の目安と考えてください。
このように、暦年贈与は、毎年110万円ずつ贈与すればいいとは限りません。保有資産の額によっては、
なお、暦年贈与は2024年から「持ち戻し」の期間が7年に延長されたことにより、これまでほどの旨味は失われることになります。今後は、「相続時精算課税」制度のほうがメジャーになっていく可能性があります。これは総額2,500万円以下の贈与について相続時まで課税の繰り延べが行われ、かつ、持ち戻しのない「年間110万円」の基礎控除を受けることができるものです。どの制度を活用するとメリットがより大きいのか、十分に考慮したうえで、相続対策を行う必要があります。
黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ 共同代表
公認会計士
税理士
\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/25開催】
相続や離婚であなたの財産はどうなる?
預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策
【2/26開催】
いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?
個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質
【2/28-3/1開催】
弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~