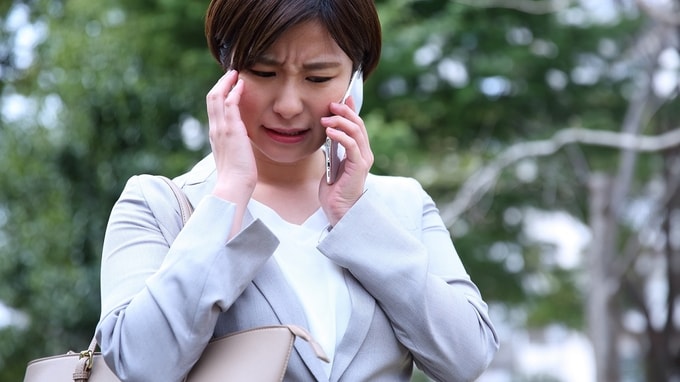妹が“頑張り損”にならないためにできる「3つ」の生前対策
長年介護などに尽力してきた相続人が少しでも報われるよう、いくつかの対処法を検討してみてはいかがでしょうか。
被相続人が亡くなる前からしっかりと相続対策を行っておくことで、不義理な相続人への遺産を減らすことができます。被相続人の協力が必要という前提ではありますが、3つの相続対策を紹介します。
1.遺言書の作成
遺言書を作成することで、遺言書の内容に沿った遺産分割を実現することができます。すなわち、親の介護を放棄した不義理な子どもに対して、「一切遺産を相続させない」という内容の遺言書を作成することも可能です。
ただし、法定相続人である子どもや配偶者、子どもがいない場合の父母(祖父母)は、相続に際して、「遺留分」という最低限の範囲で財産を取得する権利を有しています。
そのため、そのような遺言書を作成したとしても、相続人から「遺留分侵害額請求」を受けると、遺留分の金額を支払わなければなりません。もっとも、渡す財産は遺留分の金額のみになり、法定相続分よりも小さくなりますので、遺言書を作成しておくことは非常に重要です。
2.生前贈与によって財産を減らす
亡くなる時点の財産(遺産)を可能な限り少なくすることで、親の介護を放棄した不義理な子どもへの相続分を減らすことも考えられます。その代表的な方法のひとつが「生前贈与」です。
生前に介護に尽力してくれた配偶者や子どもに対して、生前に財産を渡しておけば、介護をしてくれたことへの感謝を伝えることができますし、それによって、不義理な子どもの取り分を減らすことができます。
ただし、生前贈与は特別受益として、遺産分割の際や、遺留分侵害額請求の際に考慮されることがありますので、注意が必要です。また、生前贈与をする際は、金額によっては贈与税が課されますので、税理士にも相談して進めるとよいでしょう。
3.第三者に遺贈や死因贈与をする
「遺贈」とは、遺言により法定相続人以外の人に遺産を渡す方法です。また、「死因贈与」とは、贈与契約の一種で、贈与者の死亡をきっかけに贈与の効力が生じる契約です。
いずれも相続人以外の第三者に対して、遺産を渡すために用いられる方法です。これらの方法をとることで、遺産相続の対象となる財産を減らすことができ、結果として不義理な子どもの取り分を減らすことができます。