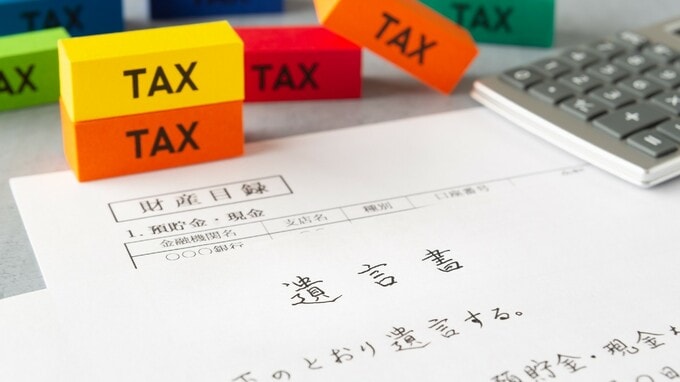「生命保険受領時」は相続税申告だけでなく確定申告も
相続が発生し、相続財産を承継した場合、相続税申告をすれば足りることも多いです。しかし、被相続人が被保険者の生命保険金を受領した場合において、契約者等によっては相続人に所得税納税義務が生じ、確定申告をしなければならなくなります。
(1)契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人、受取人が相続人の場合
→相続税の申告
(2)契約者(保険料負担者)が相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人(契約者と同一)の場合
→所得税の申告(住民税の課税対象にもなります)
(3)契約者(保険料負担者)が相続人、被保険者が被相続人、受取人が相続人の子ども(契約者と異なる)の場合
→贈与税の申告
(1)の場合、相続財産が多額となる場合、相続税の税率が高くなります。たとえば、相続税の最高税率は55%となりますので、仮に1億5000万円の生命保険金を受領する場合に、最高で8250万円の税金がかかることとなります。そこで、税額(税率)を低くするために、(2)を活用し、保険料贈与プランを検討する場合があります。保険料相当額を被相続人から相続人に贈与し、相続人が保険に加入して贈与された金銭を保険料として支払うプランになります。
このようにすることで、相続発生時の生命保険にかかる税金は所得税・住民税となります。所得税・住民税の最高税率も、相続税と同じく55%ではありますが、相続人が受け取る生命保険金は一時所得となりますので、税金がかなり低くなります。
が課税対象となります。
たとえば、5000万円の保険料を受け取るのに、3000万円の保険料を支払った場合は、
が課税対象となります。
相続税の場合は、受け取った生命保険金5000万円が課税対象となりますので、課税対象が低く抑えられます。ただし、相続税の税率や相続人の収入によっては、節税にならない場合もありますので、事前にシミュレーションをした上で、検討されることをお勧めします。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資