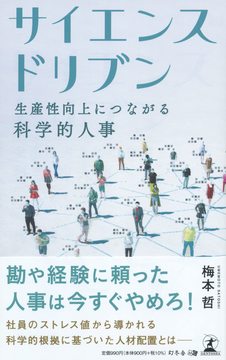【関連記事】高学歴でも「仕事ができない社員」に共通する、意外な口癖
ハイパフォーマーを上司にするだけでチームが活性化
マネージャーへの昇格基準もビジネス適応力で判定することが適切と考えられます。
リーダーによって、組織の活気に違いが出るのです。クールなリーダーが悪いとか、親分肌のリーダーが良いというわけではありません。クールなリーダーのチームに活気があり、親分肌のリーダーのチームに活気がないこともよくあることです。外見的な印象も大事ですが、リーダーのパフォーマンスの高さが重要で、リーダーのビジネス適応力の差がカギになります。
ビジネス適応力が高いハイパフォーマー・リーダーのチームには活気があり、逆は活気がないことが分かっています。したがって通常のリーダー昇格基準に加えてビジネス適応力の高い順にリーダー、マネージャーに昇格させることで組織の活力を引き出すリーダーを選出することができると考えますが、日本の組織においてはなかなかそれができません。
その理由は、年功序列型の組織が多く、長く会社にいる人から順に役職につく傾向があげられます。また日本にはプレイングマネージャーが多いことも理由に挙げられます。プレイングマネージャーにおいては、組織やマネジメントやビジネス適応力よりも仕事のスキルが重視される傾向が強いのです。
加えて、そもそもビジネス適応力という考え方がありませんでした。その概念も測定する方法もなかったわけですから仕方のないことですが、ビジネス適応力という考え方を普及し、それを活用して成果を上げる企業が一つでも増えることが私たちの使命でもあります。
ハイパフォーマーを「飼い殺し」にする日本の人事制度
日本企業では、ビジネス適応力という考え方がなく、測定もされてきませんでした。ビジネス適応力を測る指標がないため、指標に基づく正しいハイパフォーマーの育成も行われてきませんでした。逆の見方もできます。そもそもハイパフォーマー育成を行おうという気運がなかったので、育成のための指標を探ろうという動機付けがなく、そのためにビジネス適応力という考え方も生まれなかったと考えるほうが真相に近いかもしれません。
では、なぜハイパフォーマー育成を行うという気運がなかったのでしょうか。
まず日本には、ときに「悪平等」といえるほどの平等主義、公平主義が存在します。日本でもかなり崩れてきたとはいえ、いまだに多くの企業が終身雇用・年功序列の人事制度を引きずっています。その名残が新卒社員の一括採用です。海外のジョブ型雇用では通年採用が普通となりますが、日本では一部の企業を除いてなかなかそうなりません。終身雇用・年功序列では、平等性・公平性が人事評価において最優先されます。
そうなると結果的に、教育研修等で育成の主眼となるのは平均的な社員、すなわちアベレージパフォーマーに設定されることになります。いわゆるエリート教育のようなことは、少なくとも社内でおおっぴらに行われることはありません。ハイパフォーマーにとっては退屈な教育研修となり、彼らの力がうまく引き出されることにつながりません。
またハイパフォーマーは、同期や同僚と比較するとはるかに高い評価を受けることが多くなります。そうなると本人も周囲もハイパフォーマーの成長スピードに問題意識を感じません。本来ならもっともっと成長してもよい人材が、安心してしまって、アベレージパフォーマーと大差ないような成長にとどまることになりがちです。飛び級で20代・30代でも役員になれるのでしたら話は変わってくるかもしれませんが、年功序列の平等主義組織ではそのようなことは起こり得ないので、急成長しようというモチベーションも湧いてきません。
海外企業ではハイパフォーマーこそ育成対象
さらに日本には、ハイパフォーマーは放っておいても勝手に成長すると考える人が多いといわれています。グーグルやアップルなどシリコンバレーのハイテク企業では、むしろハイパフォーマーこそ育成しようという考え方があり、日本企業とは好対照です。
アスリートの世界では、コーチやトレーナーからの適切な指導・支援が必須という考え方があり、これは日本でも定着してきています。シリコンバレーには「ザ・コーチ」として知られていたビル・キャンベルというレジェンド・コーチがいました。スティーブ・ジョブズとアップル帝国を築き、グーグルを巨大企業に導き、アマゾンの苦境を救ったコーチとして知られている人物です。彼はもともと、アメリカンフットボールのコーチでした。
米国では、スポーツのコーチがビジネスのコーチとしても成功している事例があるということですが、それは考え方が共通しているからでしょう。日本ではスポーツとビジネスの人材はなかなか交流しない傾向があり、スポーツ界のすばらしい常識もビジネスの世界では顧みられないということが起こりがちです。
これもアスリートとの比較になりますが、日本でもレベルの高いアスリートは海外に出て行って、世界レベルのなかで自分の未熟さを感じながら、ハイレベルのアスリートたちと切磋琢磨することで自らを成長させています。ところが日本企業のハイパフォーマーの多くにはそのような機会がほとんど与えられていません。
梅本 哲
株式会社医療産業研究所 代表取締役
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】