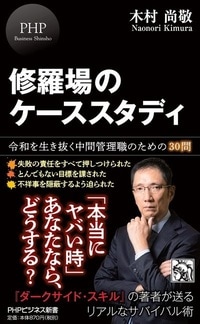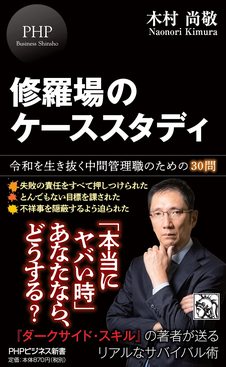※※本記事の読み方※※
●まず「ケース」を読んでいただき、2~3分かけて「自分ならこうする」という自分なりの答えを導き出してください。
●その上で、「解説」を読み、自分の考えとどこが同じでどこが違っていたかを確認してください。
●著者の「解答」は解説の最後に挙げていますが、最初から見ないようにしてください。
●著者の解答はあくまで、「解答の一例」であり、合っていた・違っていたを問うものではありません。自分の答えと違っていたら、「なぜ、違っていたのか」を改めて考えてみてください。
前任者が残した「間違った営業スタイル」を改革したい
**********************
<Case:前任者の「負の遺産」で現場が疲弊しきっている…>
前営業部長が役員に出世、海外勤務から凱旋帰国し、後任として大抜擢された自分。でも、就任して改めて部門の数字を精査してみてびっくり。前営業部長はかなり無茶な「押し込み営業」で数字を作っており、経費の無駄もかなりの額に上っている。しかも、現場は疲弊しきっている。
どう考えても早晩、このやり方は破綻する。でも、役員となった前任者はこのやり方が正しいと信じ込んでおり、何より今、営業担当役員として自分の上に君臨しているのは彼だ。
**********************
⇒Q. あなたが新任の営業部長なら、この状況をどう打開する?
「表面上は従い、水面下で改革準備を進める」のが吉
ここで絶対に避けるべきなのは、「一人で、真正面から戦いを挑む」こと。役員に「あなたのやり方はもう古い」などと宣言したところで、自分より立場の強い人に勝てるわけがありません。
正義感の強い人ほど、こうして真っ先に討ち死にします。表面上は平静を保ちながら、水面下で改革に向けた準備を進める。しばらくは良い意味での「面従腹背(めんじゅうふくはい)」でいくべきでしょう。
一人で戦うリスクを避けるには、部下を巻き込むことです。
例えば、「事業方針策定ミーティング」と称して部下を集め、自由に意見を言わせる。彼らもこれまでのやり方で疲弊しているので、くすぐればすぐに不平不満がどんどん出てくるはずです。多少、誘導尋問的に自分の思う方向に意見を持っていってもいいでしょう。
そうして、新しい方針が「チームの総意」となれば、役員も反対しにくくなり、チームも一丸となる。孤独な戦いを避けることができるのです。
新しいやり方で結果を出すまでは「我慢」の日々
ただ、ビジネスでモノを言うのはあくまで実績。新しいやり方で結果を出せなければ、当初は一丸だった部下の心さえも離れていきます。
しかも、結果はすぐに出るものではありません。むしろ、オペレーションやプロセスを変更した場合、短期的には効率が落ちるのが普通です。
リーダーに問われるのは、ここで「我慢」ができるかどうか。内心は「本当にうまくいくのか」とビクビクしていても、それをおくびにも出さず、部下に「大丈夫だ」と言い切ることができるか。
決して途中で妥協してはいけません。仮に、これまでの「人海戦術による義理人情浪花節(なにわぶし)の押し込み営業」から、「データに基づいた科学的な営業」にシフトすると決めたのなら、いくら目先の売上が惜しくても、押し込み営業はスパッとやめる。舵(かじ)を切るなら一気に切るべきです。
こうした動きに対し、役員が反撃してくることもあります。よくあるのが、部下の一人が役員と手を結び、反対勢力に回ること。まさに代理戦争です。そういう部下は放置せず、覚悟を決めて戦うしかありません。
どうしても役員が納得しないときの「奥の手」
新しい営業スタイルはチームの総意であり、かつ、実績も上がっている。それならば役員も方針転換に納得せざるを得ないでしょう。
ただ、伝え方は工夫すべきです。「押し込み営業はもうやめます」だと、過去を否定されたと感じ、役員はいい顔をしません。「属人的なスタイルからマーケティング及びチームワークの営業に変更します」などと言い換えましょう。物は言いようです。
もし、それでも役員が意見を変えず、強硬に以前のやり方を主張してきたらどうするか。これはもう覚悟を決めて「刺す」しかありません。
その際、一つの方法として「上の上」、この場合なら社長や副社長に直訴(じきそ)するという手があります。
ここで、一つ使える「ダークサイド・スキル」を紹介しましょう。それは「顧客を巻き込む」ということです。
社長と主要顧客との会食をセットし、その場で新しい方針がいかに素晴らしいかを顧客に語ってもらう。そして帰り際に社長にひと言、「でも、XX役員はいまだに過去の義理人情浪花節スタイルに固執しているのですが…」。
戦い抜くベースとなるのは、「今までの営業は間違っている」という強い信念です。リーダーになったら真っ先に、ここを考え抜く必要があります。
その上で、新しい方針が正しいという確信が得られたら、使えるものは何でも使って、変化を起こす。チームを預かるポジションになったら、こうした政治的な綱渡りもできなくてはならないのです。
木村 尚敬
(株)経営共創基盤(IGPI) 共同経営者(パートナー)
マネージングディレクター
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】