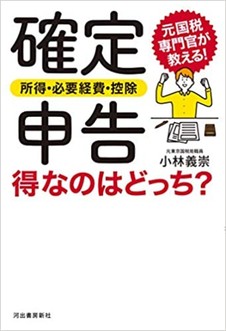「住宅取得資金」と「教育費」のサポートどっちが得か
正解:「住宅取得資金」の特例のほうが効果的
家族をもつ人にとっての二大出費が「自宅の購入費」と「教育費」です。いずれも数千万円単位の資金が必要になるので、自分の親からサポートしてもらうこともあるでしょう。
このとき、どちらの名目でサポートしてもらうかによって、贈与税の扱いが変わってきます。自宅の購入費の贈与を受けた場合に使える「住宅取得資金贈与の特例」について説明しましたが、教育費についても贈与税の特例が存在します。

そこで今回取り上げたテーマが、「住宅取得資金と教育費の一方だけを贈与してもらえるとしたら、どちらを選ぶべきか」というものです。
結論からいえば、私なら住宅取得資金贈与の特例を選びます。
教育費に使える特例は、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(以下、「教育資金特例」)と呼ばれているものです。
平成25年4月1日から平成31年3月31日までのあいだに使える期間限定の特例だったのですが、平成31年の税制改正で、2021年(令和3年)3月31日まで延長、今回の税制改正で2023年(令和5年)3月31日までと2年延長が決まりました。
この特例を使えば、直系尊属(両親や祖父母など)から子や孫に対する教育資金の贈与が、1500万円まで非課税になります。
教育資金特例を使うには、以下の手順をふむ必要があり、通常の贈与のように、一度お金を受け渡しすれば終わりというものではありません。
①信託銀行等で、教育資金贈与用の非課税口座を申し込む
②学費などの領収書等を提出し、資金を払い戻す
③一定の条件に該当した場合、信託銀行等との契約が終了する
④非課税口座に残金があれば、贈与税の対象になる