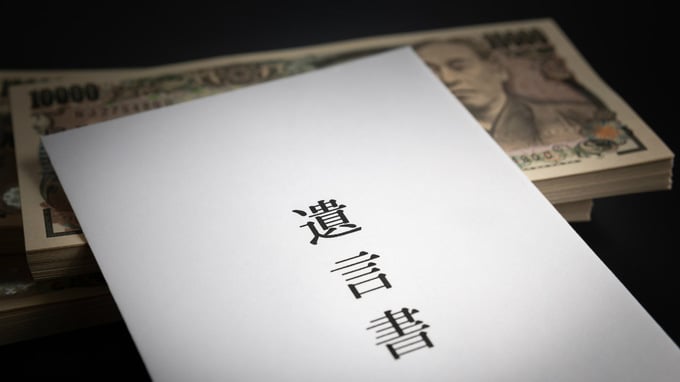1年以内に請求できなければ「遺留分」は無効になる?
相続人は次男である私と長男だけです。
父がこのような遺言を書いたことが納得できず、兄である長男に対して、「父の遺言は置いておいて、兄弟で話しあって遺産を分けよう」と遺産分割協議の申し入れをしていましたが、兄はまったく意に介してくれず、父が死んでから1年以上が経過しています。
遺留分という権利があるということを知りましたが、弁護士に相談したところ、原則として、父が亡くなってから1年以内に請求しなければならなかったといわれました。
私は遺産分割協議の申し入れしかしておらず、遺留分を請求する、とは兄にいっていないため、1年以上経った今となってはもう遺留分は請求できないのでしょうか?

遺留分減殺請求権の有効期間は原則として1年だが…
A.原則として、遺留分減殺請求権の行使となりませんが、例外的に行使となる場合もあります。
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間これを行わないときは、時効によって消滅するものとされています(民法1042条前段)。
したがって、遺留分を侵害された相続がなされた場合には、速やかに内容証明郵便で遺留分減殺請求の通知を送って消滅時効の成立を防ぐ必要があります。
しかし、相続開始後しばらくの間弁護士がつかなかったような事案では、遺留分の減殺請求の裁判において、死後1年間の間に遺留分減殺請求をしたか、という消滅時効の問題が争点になることが多々あります。
遺産分割協議や遺産分割調停の申立てを行っていた場合
何もしないままに1年間が過ぎてしまっているような場合はどうしようもありませんが、ここで問題となるのは本件のケースのように遺産分割協議の申入れや遺産分割調停の申立てはしていたが、遺留分減殺請求権を行使すると明示した通知などをしていなかったような場合です。
この点について、裁判例の傾向は、遺産の分割請求と遺留分減殺請求というのは、その要件、効果を異にするので、原則として遺産分割協議の申し入れや遺産分割調停の申立てをしても遺留分減殺請求の意思表示をしたことにはならず、消滅時効は進行すると解釈されています(東京高裁平4年7月20日判決)。