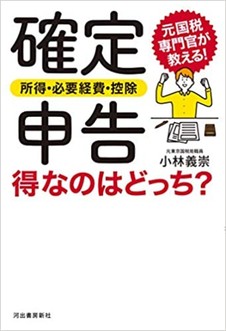「確定申告しない」は節税のチャンスを逃している
正解:フルに節税するには「確定申告」が必須
本連載のテーマは「確定申告」ですが、そもそも確定申告をやったことがないという人も少なくないのではないでしょうか。
節税をフルにおこなうためには確定申告は必須事項なのですが、人によっては確定申告をせずに済ませることができます。

これは裏を返すと、「節税のチャンスをみすみす逃している」ということです。
そこで、「そもそも確定申告とは何か」をまずは説明しましょう。節税を考えるには、「確定申告でできること」を大まかに理解しておくことが大切です。
確定申告の本来の意味は、「日本の税金に関する申告手続き」というものです。日本には所得税や贈与税、法人税、消費税など複数の税金があり、それぞれの税金について確定申告のルールが設けられています。
ただ、一般の人に関係するのは、ほとんどが「所得税」の確定申告です。所得税は、簡単にいうと、「個人の稼ぎに対する国税」ですから、誰にでも関係のある税金といえます。
そういった意味で、本連載においては特別な説明がない限り、「確定申告」という言葉が出たら、「所得税の申告手続き」をイメージしてください(あとの稿で贈与税の確定申告についても触れます)。また、2013年から2037年までの期間は所得税に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として加算されていますが、本記事で用いている「所得税」という言葉は、復興特別所得税を含むものとしてご理解ください。
つぎに、所得税の基本的なルールを理解しておきましょう。所得税は、毎年1月1日から12月31日までの個人の所得に応じて課せられるものです。
確定申告をするとき、自分の1年分の所得税を計算して、その結果を「確定申告書」に記載したうえで、翌年3月15日(休日の場合は翌日)までに税務署に提出します。確定申告の情報は税務署から地方自治体に引き継がれるので、申告が終わってから、地方税である「住民税」の通知がくるという流れです。つまり、確定申告は所得税と住民税を決めるうえで欠かせない手続きなのです。