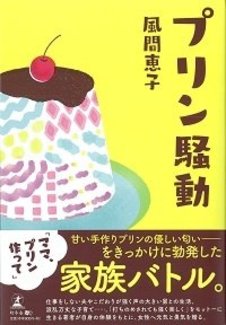「もしもし、私」とハスキーな女性の声がした。
すると、「もしもし、私」とハスキーな女性の声がした。やけに慣れ慣れしい。飲み屋のママかな?
女の勘はさらに仕事をした。
答えずに無言のまま相手の様子を窺っていたが、相手も同じ事を思ったのか、慌てて切った。ひたすら怪しいと直感し、頭上で電球千ワットが光った。ただの関係ではない、それ以上の親密さを声で感じとった。私は、夫には携帯のことは言わなかった。
夫は何も知らずに、夜の街へと消えて行った。ムスクの香りをかすかに残して。
一人、私はベッドに入り眠ろうとしていた。しかし、頭の中が散らかったまま、ザワついて眠れなかった。
時計を見ると、十一時を過ぎていた。明りを消して目を閉じてみる。神経は冴え渡って寝るタイミングを逃していた。私は静かに目を開いて天井を見つめた。寝室は十二畳だったが十二畳分の広さではない。
今私の感覚的に映し出された天井は宇宙より広く終わりのない無限の闇が墨汁を吸い込んでいく魔物に見えた。一寸の光も射さない。
この闇が私の全身を覆い隠してしまう。自分の存在さえも闇と融合し存在していないのと同様に感じられた。今まで感じたことがない感覚。
「何?」
淋しいとか悲しいとかの種類には属してはいない。未知との遭遇だ。その正体を暴きたかった。そうしなければ、朝は訪れないような気がした。広がる闇の奥底をひたすら深く凝視した。
やがて、私の脳裏に白く浮かび上がった文字があった。