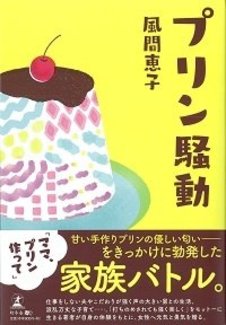夫の脱出
子供たちが生まれてから十一カ月が過ぎようとしていた寒い夜。
時計は十一時を少し過ぎた頃、夫と私は二人で部屋にいて寛いでいた。夫はテレビを観ていた。私はドレッサーの前に座り保湿クリームを塗り終えようとしていたその時、夫は顔を私の方へ向けてポツリと言った。

「オレは独りになりたい」
私は一瞬耳を疑った。人として非常識で愚かな言葉だった。
部屋には二人きりだ。子供たちは姑が寝かしつけてくれていた。姑は孫を大変可愛がってくれた。「目に入れても痛くない」と言っていた。この頃は姑はもう専業主婦だったため、孫へ愛情を注いでくれるのはありがたいと感謝している。
舅も、日曜日になると、廊下にあるソファに孫をチョコンと座らせ愛でる表情で愛情をテレパシーで送っているのを何となく感じられた。やはり姑同様に、「目に入れても痛くない」存在なのだろう。
みんなからの愛情を受けて育つことは、子供たちにとってとても大切なことだと思う。多くの愛からは豊かな心が育つ。豊かに育った子供は豊かな感情の人間に成長するのだと自負していた。たとえ家族の中の一人だけの愛情が注がれないとしても充分な愛情は人間らしい人格形成には問題は生じないと感じている。
「足るを知る」ことは大事なことである。不足はリアルに自分に取り込まなくても良いのである。私は自分なりに考え、時には子育ての先輩としての姑のアドバイスも聞きながら子育てをしていこうと考えていた。
今のところ、些細な疑問やつまずきは時々あるにしても順調に子供たちは成長していた。私の生きる中心だった。生きていることを実感できた。
しかし、夫の一言が、私の幸せな心を凍結させた。血の気が引いた。