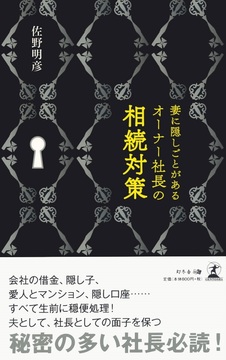法律的な親子関係を第三者に示す方法とは?
今回の事例ではあまり関係ありませんが、「本当の子供かどうか」が問題となる場合があります。法律的には「本当の母親かどうか」という点は疑いがありませんが「本当の父親かどうか」は第三者からはわかりません。そのため、法的な効力をもつ「認知」という手続きがあるのです。
認知以外の方法で父子関係が認められるには「嫡出推定」という方法があります。嫡出推定とは、生まれてきた状況などから「その男性の子供に違いない」と推定することです。
たとえば結婚しているというのは「嫡出推定」が成立する大きな要素です。ただしこれについても細かな規定があり、民法772条では結婚してから200日以内に生まれた子供については「嫡出推定」を行わないことになっています。
つまり法律をそのまま適用すると、いわゆる「できちゃった婚」の場合には、夫はその子の父親だとは推定されない可能性があるのです。これは妻が結婚前に付き合っていた男性がいるかもしれないということを排除できないからです(いろいろな判例があり法律家にお任せする微妙な分野になりますが、父子関係に争いがなければ、現実的には結婚している二人の子供となるでしょう)。
このように、法で定められた条件に当てはまれば「嫡出推定」が適用されます。そうでない場合には、法律的な父子関係を結ぶために「認知届の提出」という手続きを取る必要がでてきます。非嫡出子は「嫡出推定」に必要な条件に当てはまらないため、父親の認知がなければ父子とは認められないのです。こちらの場合も細かな条件はありますが、父親側にその意思があれば認知は簡単にできます。役所に認知届を提出し受理されれば戸籍に父親として記載され、法的に正式な父子と認定されます。
認知して父子関係が成立すると、出生したときに遡って法律上の親子関係に基づく「相続権」や「扶養義務」が発生します。非摘出子であってもこの権利関係は嫡出子と同じです。一般的に母子家庭の生活は不安定なものです。側にいて一緒に生活できないのであれば、最低でも認知という形で気持ちを母子に示すことが必要です。相続はそこからスタートとなります。
出生時まで戸籍を遡れば認知の事実も明らかに
●対策1 認知を知られたくない時には転籍という手段がある
認知をすると父子ともに戸籍の表記が変わります。子供の戸籍には「父」の欄に認知した男性の名前が入り、父の戸籍には左記のような記述が加わります。
「平成○年○月○日○○市○○ ○番地木下華子同籍義男を認知届出」
このため、もし家族が戸籍を閲覧する機会があれば、認知した隠し子がいることがわかってしまいます。ただし、この一文は転籍(戸籍を別の住所に移す)などにより新しく戸籍を作り直した時には記載されなくなります。あまり知られていませんが、戸籍は実在する場所であれば、日本中どこでも好きな場所に移すことができます。自分とはまったく関係がなくても、六本木ヒルズや田園調布のお屋敷を本籍地にすることが可能なのです。
わざわざそんな場所にするのは不自然ですが、「我が家のルーツである本家の場所に本籍を移したい」など、適当な理由を付けて転籍することは可能です。費用はほとんどかかりませんから、家族にどうしても知られたくないなら転籍の手続きをとることで、転籍した後の戸籍を見るだけでは隠し子の存在を知ることはできなくなります。ただ、転籍しても戸籍の見かけが変わるだけなので、以前の戸籍を遡れば、認知した子供がいることは判明します。
社長が亡くなり相続が発生すると、法定相続人を特定するため社長の出生から全ての戸籍を入手します。最終的に法定相続人全員の合意がなければ、法的に相続が正しく完了したと認められないためです。大きな額の相続ではほとんどの場合、税理士や弁護士などの専門家が依頼されて実務を引き受けます。
遺産分割を決めた後に、隠し子など把握していなかった法定相続人がいたことが判明すると、遺産分割作業がやり直しとなります。そのため相続が発生したら、まず相続人を特定するために、全ての戸籍を出生時まで遡って調べるのです。認知している子供がいることはその過程で明らかになるので、転籍はそれまでの一時しのぎと考えておくべきです。
子供側から認知を求められる「強制認知」
父親に求めても認知してもらえない時、子供には裁判所に「強制認知」を求めるという手段があります。家庭裁判所に訴えることで、強制的に父子関係を認定させる手続きです。子供の側から認知を求めるこの手続きは二段階に分かれています。
まず、子供の訴えを受理した家庭裁判所は、父親とされる男性に対して「認知するのですか?」と合意を求める調停を行います。そこで男性が拒否した場合、子供の側は「認知請求訴訟」を起こすことができます。この訴えが提起されると、両者の合意のもとDNA鑑定が行われ、遺伝学的な判定が求められるようになります。さらに、その結果を基に審理が行われ、DNA鑑定で父子関係が認められた場合には、法的に父子と認める判決が下されるのです。
父親の死後から3年以内であれば認知請求が可能
この事例の二階堂社長のように、死後に認知を求めて請求を起こされることもあります。これは「死後認知」と呼ばれる手続きで、隠し子の側は父親の死から3年後までこの訴えを提起できます。
「死後認知」の訴訟では本来は訴えの相手となる父親が亡くなっているので、便宜的に検察官が訴えの相手となり、判定についてのチェックを行います。裁判所では、兄弟姉妹など近親者の協力を得てDNA鑑定を行い、父子関係を判断します。兄弟姉妹などがDNA鑑定を拒否すると審理は複雑になりますが、当時のさまざまな事実関係によって検討が行われ、認められる可能性もあります。
DNA鑑定で父子関係が認められると子供の請求が通り、晴れて認知されることになります。強制認知と同じく、子供の認知請求の権利は誰にも侵害できない権利なのです。生前の認知がどうしても難しい場合には、遺言書で認知をしておくのもよいでしょう。生前に認知するだけでなく、子供には両親の愛情を相続させることが一番大切です。