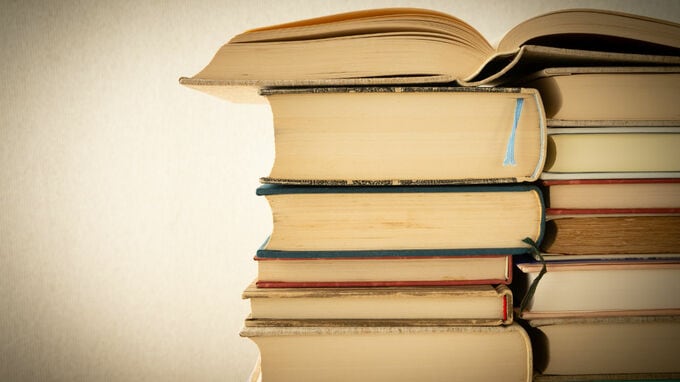禁じられ、拒まれた愛の昇華だった
拒まれるテーマと逆のテーマは恕(ゆる)されるというテーマであるが、このテーマはいつも死と隣り合せである。例として『絹と明察』における駒沢善次郎は死が近づくにつれて、敵を恕(ゆる)し、また『憂国』で切腹の直前に、「何かが宥(ゆる)されている」という文章がある。
以上に述べたことをまとめると、三島由紀夫は死ぬことによって今まで拒まれていたものがゆるされ、黄金郷にもどることを望んでいたのであって、これ故に『憂国』において、死は至福となるのである。
さて、黄金郷とはいかなる場所かを引用すると、「彼が久しく誰にも言わずに夢見てきたこの大がかりな夢想のうちでは、彼が男らしさの極致におり、女は女らしさの極致にいて、お互に世界の果てから来て偶然にめぐり合い、死が彼らを結びつけるのだった……。彼らは人間のまだ誰も行ったことのない心の大海溝の奥底へ下りてゆく筈だった」(『午後の曳航』)。
黄金郷が幼年期であることはすでに述べた。この事実を引用文に合せ考えると、幼年期の女は母にほかならず、また大海溝も海=母であるから、黄金郷は幼児期の母のもとと言えるであろう。故に、死の場所は海=母の近くでなければならないのである。
それがゆえに、『豊饒の海』「第二巻 奔馬」の最終の場面で勲は黒光りに映える海の見える所で切腹を遂げるのであり、『真夏の死』は、海での死であり、『午後の曳航』で龍二は海に面した丘で殺されることになり、『憂国』では、中尉の言葉として、「俺の切腹を見届けてもらいたいんだ」と妻に頼まなければならないのである(ここでは妻=母)。
小説に現れた母の像をもう少し追うと、それは『山羊の首』に書かれた香村夫人であり、また山羊の頭そのものが母の象徴なのである。『金閣寺』には見事に母の像が描かれている。父の像も描かれてはいるが、母の像に比べるとその密度は少し劣る感がある。
これに対して金閣は小説の中で母の象徴そのものとして燦然と屹立しているのである。三島由紀夫には禁じられた愛を描いたものが多いが、これは母への禁じられ、拒まれた愛の昇華と考えられる。例としては、『春の雪』『頭文字』『鏡子の家』『沈める滝』『愛の渇き』『獣の戯れ』『美徳のよろめき』などがある。
さて、これまで私は三島由紀夫がいかに幼児期の母に憧れていたかを書いてきたが、これについて現実面から確かめる。