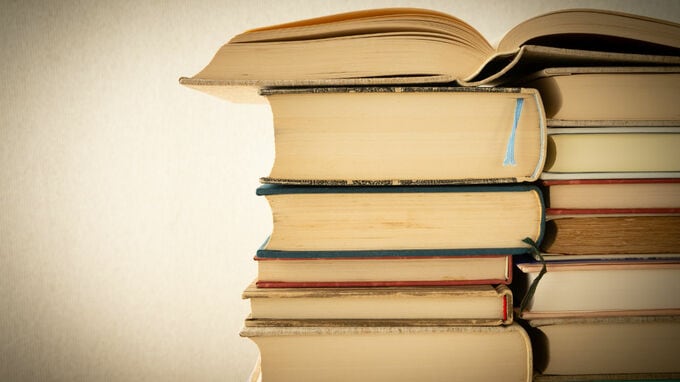三島には十才の頃まで「女装欲」があった
彼は『母を語る』(潮文社)という随筆中に「紫陽花の母」という小文を書いているが、この中で、「私は長い間、祖母に育てられていたおばあちゃん子だったので、母と一緒に暮すようになってからは、すっかり母に甘えたい気持になっていた……文学というのは結局は自己独立の仕事ではあるとは言っても、母親的な庇護が必要なのだと思う」と述べている。
三島由紀夫が母に拒まれていたというはっきりとした現実の裏付けはないが、先に述べたように母から離されて、祖母のもとで育てられていた事実以外にも五才の時に弟が生まれたこと、そしてこの弟は祖母に育てられることはなく、母親のもとで育てられたことも、重要な意味があったのではないかと思われる。この頃三島由紀夫が罹患したという「自家中毒症」は心身症であり、彼が経験した精神的ストレスを示しているのではないだろうか。
彼はいかにして、この拒まれたものを得ようとしたのであろうか。これを説明するものの一つに、十才の頃まで続いたという女装欲がある。すなわち、母から拒まれた三島由紀夫は自ら母になろうと努力するのである。
この事実については、『仮面の告白』に、「私は、今度は祖母や父母の目をぬすんで、妹や弟を相手にクレオパトラの扮装に憂身をやつした。何を私はこの女装から期待したのか?」とある。また十才以後もこのような傾向があったことは、「丸山明宏にはかなわない」という彼の言葉からも明らかである。
私が海について述べたのは、三島由紀夫にとって海は母の象徴であり、彼は海=母に憧れていたが、これに拒まれていたので、死をもって恕(ゆる)され、母のもとに帰るか、または女装することによって、自らが母親になることによってこの拒みを乗り越えようとしたということである。
三島文学において、一度の例外もなく、太陽は父の象徴であった。太陽こそは彼が近づこうと努力し、またそれに対抗しようとしたものであり、それに負ける(死ぬ)ことによって、母のもとに帰ろうとした彼にとって、海とは異なったもう一つのテーマである。
まず、太陽と死が、いかに緊密な関係を持っているかの例を引用すると、
「正に刀を腹へ突き立てた瞬間、日輪は瞼の裏に赫奕(かくやく)と昇った」(『豊穣の海』「第二巻 奔馬」新潮社)。
「あれは大そう緊密で均質な夏の日光で、しんしんと万物の上に降りそそいでいた。戦争が終っても少しも変らずにそこにある縁濃い草木は、この白昼の容赦のない光りに照らし出されて、一つの明晰な幻影として微風にそよいでいた。私はそれらの葉末に私の指が触れても、消去ろうとしないことにおどろいた」(『太陽と鉄』)。
三島由紀夫にとって不思議なのは、強い太陽に照らされた草木が死なずに存在しつづけることなのである。『真夏の死』において、太陽のもと、海の中で死ぬという理想を三島由紀夫は描いたのである。
これを現実の言葉に翻訳すると、父の目前で死に、同時に母のもとに帰りたいという願望を描いていることとなる。このことこそ、三島由紀夫が、「われわれ楯の会は自衛隊によって育てられ、いわば自衛隊はわれわれの父でもあり、兄でもある」(『檄』より)、という自衛隊で切腹した潜在意識的理由なのである。
彼が総監室にもどり切腹をした理由の一つは、総監という父親像の目前で死ぬことであったであろうと思われる。