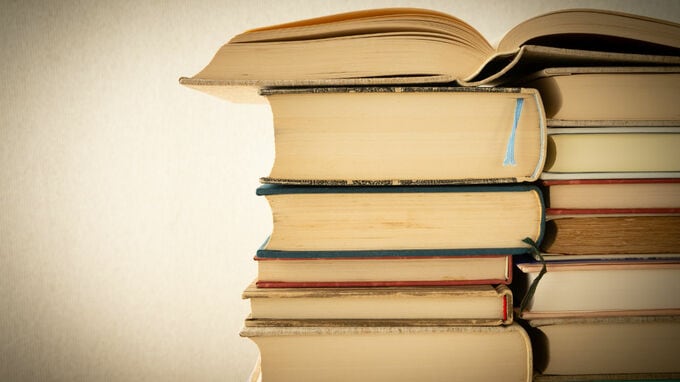海は恐ろしい物、憧れの対象、母以外の何物でもない
私が三島由紀夫の作品を読みはじめたのは大学生になってからのことである。しかし、本当の意味において、三島由紀夫を理解したのは、彼が切腹を遂げてからだと思う。それ以前は作品の華麗な表現や、アイロニイ、物語性を楽しんでいたにすぎなかった。
事件後、私は作品を読み直し、さらに評論文を読み、日常生活を知った。このようなある日、『金閣寺』を読み続けるうち、私はふと、金閣は三島の母の象徴ではないかと思いついた。この時より以降、文章を精神分析的な注意をもって読み進めた。
この方法によって、何の変哲もない土地から、遺跡が発掘されるように、表面的な物語の下から無意識の物語が現れたのである。私は、この無意識の物語が正しいか否かを、他の小説、評論、および、日常生活における行動によって吟味した。
この結果、彼の純文学的な作品はすべて、この無意識の物語のバリエイションであって、また彼の同性愛的傾向、ナルティシズム、ロマンティシズム、死への憧れ、切腹といった、一連の中庸からのずれ、といったものはすべてこの無意識から説明できることがわかり、無意識の物語は吟味に耐えたのである。
作品はすべて三島由紀夫の空想にすぎない、空想を分析しても何物も得られないという批判に対しては、三島由紀夫自身の言葉を引用して答えとしたい。
「結論から先に言うと、私の方法的努力は、最終的には、潜在意識の活動をもっとも敏活にするためのものである」(『わが創作方法』/『私の遍歴時代』三島由紀夫 講談社)
一、海
海は、三島由紀夫の作品の中で重要な位置を占めている。『花ざかりの森』『豊饒の海』『海と夕焼』『岬にての物語』『真夏の死』『獣の戯れ』『午後の曳航』『剣』『月澹荘綺譚』『潮騒』などは、この例である。これらの作品群に描かれた海はすべて、三島由紀夫が幼年時代にとらえていた母の像と同一のものなのである。
このような象徴としての海を信ずることができない人のために、ヘミングウェイの『老人と海』からの引用を挙げると、「海のことを考える場合、老人はいつもラ・マルということばを思いうかべた。それは、愛情をこめて海を呼ぶときに、この地方のひとびとが口にするスペイン語だった。海を愛するものも、ときにそれをあしざまにののしることもある。が、そのときすら、海が女性であるという感じはかれらの語調から失われたためしがない」(福田恆存訳)。
この引用文はもちろん、海がスペイン語では女性名詞であるという事実に基づいているが、それ以上のものもふくんでいることを認めるのも容易である。
さて、三島由紀夫にとって海は本当に母の象徴であろうか。最もわかりやすい文章を、二例挙げると、
「まわりの海は女に似すぎている。その凪、その嵐、その気まぐれ、夕日を映した海の胸の美しさは勿論のこと。しかし船はそれに乗って進みながら、不断にそれに拒まれており、無量の水でありながら、渇きを癒すには役立たない」(『午後の曳航』)。
「女はおそれの対象である海になべての信頼(たより)をささげ、その袖にいっしんに縋っていたのである」(『花ざかりの森』)。
さて、海が女性であり、その胸が強調され、その袖に一心に縋っていたという表現を総合して考えると、これは母以外の何物も考えられないのである。
次に三島由紀夫が描いた海をこまかく見てゆくと、海は上記の引用文からわかるように気まぐれなものであり、美しく、拒みもするが、信頼をささげ、すがりたい物である。『花ざかりの森』から引用をもう一つとりあげると、「海への怖れは憧れの変形ではあるまいか」とある。
すなわち海は恐ろしい物であるが、憧れの対象でもあるのである。