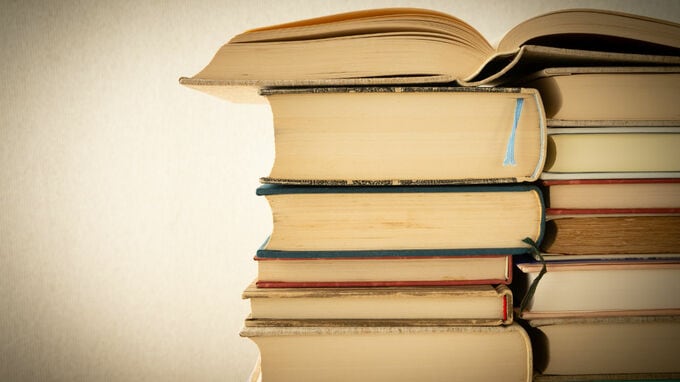「ロマンチックの病を病んでいるのかしれない」
切腹の時、三島由紀夫は剣(すなわち鉄)によって象徴化されている。自からは剣となって、母の胎内(三島由紀夫自身が母となって――女装の場合と同じ)へともどろうとするのである。
これはオットー・ランクの出産外傷または胎内復帰願望の理論と一致するものであり、このような観点からのみ、『仮面の告白』の冒頭「永いあいだ、私は自分が生れたときの光景を見たことがあると言張っていた」ことが説明されるのである。
三島由紀夫が死の衝動と自から言っていたものは、フロイトが述べているものとは異なったものと思われる。「少年時から青年期のはじめにかけて、私はいつも死の想念と顔をつき合わせていたような気がする」「私の死の欲求には、ますます現実離れのした、子供らしい夢想がからまるにまかせた」(共に『小説家の休暇』)。これらは死の衝動ではなく、胎内復帰の願望なのである。
三島由紀夫は大ロマンティストであった。彼自身の言葉によると「私は生来、どうしても根治しがたいところの、ロマンチックの病を病んでいるのかしれない」(『私の遍歴時代』)のである。ペールギュントが初恋の人に抱かれて死に、さまよえるオランダ人が最後に女性に救われるように、彼は最後に母に恕(ゆる)されて死ぬことを望んでいたのである。
私がここに述べたことをまとめると、三島由紀夫にとって胎生期および、幼児期こそ黄金の時代であったこと、この時期にもどる方法として、死をもって恕(ゆる)され、母の胎内に帰るために切腹を行なったこと、また父は子供の頃に偉大に思えたと同様に、彼が成人した後も、偉大であって欲しく、母に憧れる三島由紀夫を罰する(処刑する)ことを願っていたことである。
堀口 尚夫
精神分析医(American Institute For Psychianalysis, 1980年9月)
精神科専門医(The American Board Of Psychiatry And Neurology, 1979年4月)
ニューヨーク州医師(1977年9月)