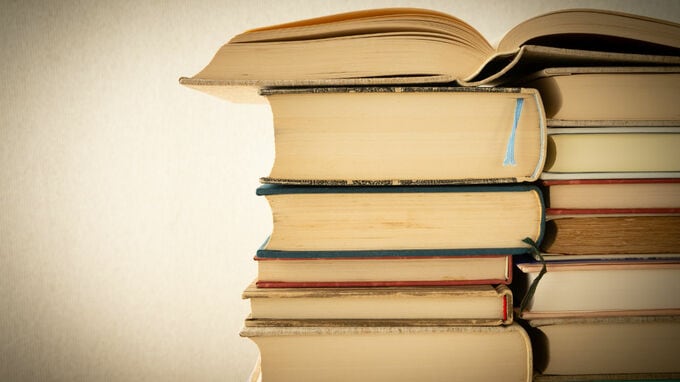とはいえ、常識的な母親のイメージから食い違っている
『仮面の告白』の第二章、最終部分に、「私は人生から出発の催促を受けているのであった。私の人生から? たとい万一私のそれでなかろうとも、私は出発し、重い足を前に運ばなければならな時期が来ていた」とあるが、これは幼年期からの出発を意味しており、この幼年期からの出発を三島由紀夫はしぶしぶ認めざるを得なかったのである。
『仮面の告白』において、前半と後半の文学的密度の違いの秘密はここにあるのだ、三島由紀夫はもうすでに一等すばらしい幼年期を終えてしまったのであって、この黄金郷にはもう帰ろうにも帰れないのである。
このようにもう経験してしまったことを色々な形で三島由紀夫は表現している。二つほど例を挙げると、「たしかに遠い過去に、私はどこかで、比(なら)びない壮麗な夕焼けを見てしまったような気がする。その後に見る夕焼けが、多かれ少なかれ色褪せて見えるのは私の罪だろうか?」(『金閣寺』新潮文庫)。
また『風景』(一九六三年七月号)において、「変質した優雅」と題する大原御幸の評論にも見てしまったことの恐ろしさを書いている。三島由紀夫にとって、幼児期の恐ろしい経験、美しい経験こそ、その全生涯をつらぬいていたものである。
上述したように、三島由紀夫は海=母を、さまざまな表現でその性格を描いているが、その中には常識的な母親のイメージから少し食い違う描写が二、三ある。すなわち、母が彼を拒む存在であり、また恐ろしいものとされていることである。
拒むという表現は、右に引用した『午後の曳航』のみではなく、『海と夕焼』においても、安里の心には「いくら祈っても分からなかった夕映えの海の不思議」があり、また『金閣寺』にも、何度も金閣が拒む場面がくり返されており、『近代能楽集』中の、「綾の鼓」「班女」にも書かれている。
拒まれることは、彼の文学の一つの重要テーマなのである。
これは三島由紀夫にとって、幼児のある時期に母親から拒まれた体験があり、また、拒まれる以前の黄金郷にもどることもまた拒まれていたと彼が感じていたことが原因であろう。
この幼児体験がどのようなことであったかを彼の記述からさがしてみると、彼は生後まもなく、母から引き離され、父方の祖母に育てられたという事実につきあたる。三島由紀夫が母に会えるのは定められた授乳の時だけで、それ以外の時は祖母と共にすごしたという。これは祖母による決定であって母の拒否ではないのであるが、授乳の時間が終わるたびに引き離された幼い三島が、母による拒絶と感じたとしても不思議ではないのではないか。