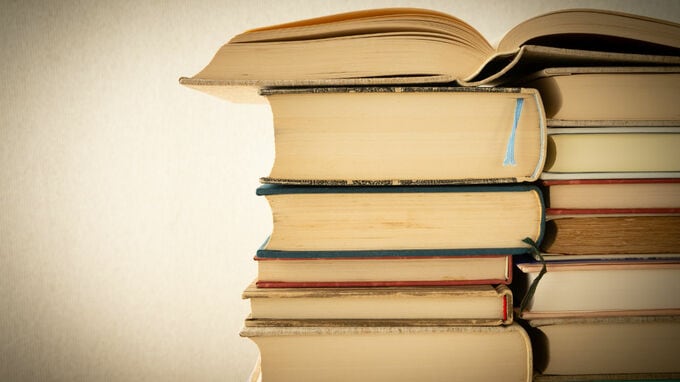「心安く死ね。その方たちはただちに死なねばならぬ」
三島由紀夫が終戦後の社会に対して不満を抱いていたことは、多くの人々が指摘しているが、これは、父親的であると三島由紀夫が感じていたものが終戦後の社会で力を失っていったことと関連があると私は考えている。父親的なものというのは、三島由紀夫の感じ方によれば、天皇制であり、自衛隊であり、権力でもある。
これ故に「太陽を敵視することが唯一の反時代的精神であった私の少年時代に、私はノヴァーリス風の夜と、イェーツ風のアイリッシュ・トゥワイライトとを偏愛し、中世の夜についての作品を書いたが、終戦を界として、徐々に私は、太陽を敵に回すことが、時代におもねる時代が来つつあるのを感じた」(『太陽と鉄』)という文章を書いたのである。
これを言い換えると、戦後の社会では権力にたてつくことが時代におもねることになった、ということになる。このようなことは三島由紀夫にとって、いさぎよいことではないのである。
戦後社会における父親の弱体化は、彼の文学の中でよく取り上げられるテーマである。たとえば『鏡子の家』における鏡子の夫の不在、『獣の戯れ』における草門逸平、『愛の渇き』における杉本弥吉、『沈める寺』における菊池祐次郎、『朱雀家の滅亡』における朱雀経隆、『美徳のよろめき』における節子の夫、『金閣寺』における老師がある。
三島由紀夫にとって理想的な父とは、『英霊の聲』にあるような天皇、すなわち「心安く死ね。その方たちはただちに死なねばならぬ」と仰せられる天皇といったような像であったのだ。戦後の社会ではこのような像は全くくずれてしまった。三島由紀夫を造作なく押し殺すような権力はどこにもないのである。このことは死によって幼い日の母のもとに帰ろうとする三島由紀夫にとって絶望的な状況になったことを意味する。
これまで、太陽は父の象徴であることを自明のごとく使ってきたが、もう少し説明を加える必要があるかもしれない。
『午後の曳航』に「南の太陽の別名である大義の呼び声」という表現がある。この大義という言葉は、分析的に言うと超自我に属するものであり、父親的響きを持った言葉であるから三島由紀夫は同義語としたのに違いない。
また『太陽と鉄』の最終部分に「イカロス」と題する散文詩を書いているが、ろうで固めた羽をつけ太陽に近づきすぎ、海に落ちたという周知の物語を借りて、ジェット戦闘機に搭乗した体験を表したのは、彼が父=太陽に罰せられ、死の後、母=海にもどる、という幼児期からの願いをここでもくり返していることになる。
海が母、太陽が父を表していたのに対して、鉄は三島由紀夫自身を表している。