あまりにも現実と酷似『首都感染』は予言の書か?
小説の映画化や著者の死を契機に、書店の棚を温めていた文庫本が急に売れ出すことはよくある。だが、出版社や著者の予期せぬところで、つまりは今回の新型コロナウイルス出現といった社会現象が引き金となって一気に売れ出す本は珍しい。
コロナ禍が続く中、高嶋哲夫氏の『首都感染』(講談社文庫、2010年刊、2013年文庫)が着実に売り上げを伸ばしている。ピーク時の大型書店では、一時品切れになる店も続出した。
「今年に入って8回重版し、初版から累計17万8000部となりました。もともとロングセラーとして読まれ続けていましたが、今回のコロナで覚醒。3月中旬に重版部数の単位が数千から数万に上がったとき、ヒットを確信しました」(講談社文庫出版部)。
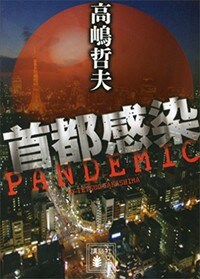
物語の舞台は20XX年、サッカー・ワールドカップ開催中の中国。中国が決勝進出を決め国中が盛り上がる中、片田舎の雲南省で致死率60%の強毒性インフルエンザが出現する。中国政府はこの事実を隠ぺいするが、大会は中止に追い込まれた。しかし時すでに遅し。世界中から観戦に訪れたサポーターが帰国すると同時にウイルス感染は拡大し、世界中でパンデミックが起きるといストーリーだ。
W杯開催中という設定や発生源(武漢市は湖北省)こそ異なるが、日本に感染者が出てからの政府の対応や社会の動きは、ここ数カ月のわれわれの実体験と見事に合致する。潜伏期間が過ぎるまで帰国者をホテルに隔離し、検疫強化のため空港を封鎖し、外出の自粛要請をし、学校を一斉休校とするなど、まるでタイムマシンに乗って10年後の世界を取材してきたかのようなリアルさがある。
あまりにも現実と酷似していることがインターネット上で話題になり、書店に足を運んだ若者も少なくなかった。中には、『ノストラダムスの大予言』 ならぬ“予言書”とみる向きもあったようだ。表紙タイトルの下にルビのようにふられたPANDEMICの赤くにじんだ文字が、目に見えないウイルス感染の不気味さを増幅させる。
ところで、重版・増刷の決定はどの部署が下すのだろうか。営業、販売、編集、社長……、出版社によって違うようだ。
「弊社の場合、通常、販売状況や受注数などを勘案して販売部と講談社文庫出版部(=編集部)が相談の上判断します。増刷にあたり、表紙装丁や帯などには一切手を加えませんでした。需要に増刷が追いつかない時期もありました」と文庫出版部は言う。




























