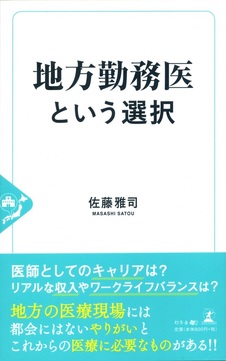「末期がんの患者」を病院に留めておくことは難しい?
がんは、今や国民の2人に1人がかかるといわれる病気でありながら、いまだに謎の多い病気でもあります。
一口にがんと言っても人により症状や進行する速さはまったく異なります。あっという間に腫瘤が大きくなり、気づいたときには手遅れというケースがある一方で、非常にゆっくりと進行し、発症から10年以上も一定以上のQOLを保ちながら暮らせるケースも見られます。
がん細胞の種類により、転移の仕方も異なります。短期で全身に転移するがんもあれば、ほとんど転移しないがんもあります。苦痛の感じ方もさまざまで、全身に転移していても長い期間、比較的元気に過ごせる人もいれば、転移が局所にとどまっている段階から、ひどい苦痛を訴える人も少なくありません。
患者によって、治療反応もさまざまです。近年では、オプジーボなどの免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬など、新しい薬がいくつも登場し、ある程度の成果を上げられるようになりました。
とはいえ、薬が効かないケースや間質性肺炎などの副作用がひどく、薬剤を使い続けられないケースもあり、依然として治療の難しい病気であることは確かです。抗がん剤がよく効いていた人でも、やがてがんに耐性ができてしまうと反応しなくなります。下がっていた腫瘍マーカーの数値が上がり始めると、次の手段を選ばねばなりません。
ある程度の期間にわたってがんと闘ってきた患者の場合、反応する治療法がなくなってしまうことがあります。そうなると多くの病院は「末期がん」と診断し、治療を諦めます。
たとえ、その患者がまだまだ元気でQOLを高く保っていても、何も治療できずに最期の時を待つ「末期がん」の患者は、治療を目的とする急性期病棟で看護すべき対象ではないというのが、多くの病院の考えです。
したがって「末期がん」と見なした患者に対して、多くの病院は退院してベッドを空けるよう要請します。中には治療中から「次の受け入れ先」を探しておくよう求める病院も見られます。
治せない患者をほかの病院へと送り出すのが急性期病院の基本姿勢であり、現行の医療制度ではそのように位置づけられているため仕方がないのですが、患者は心身ともにダメージを受けます。ただでさえ心細く不安だらけの中、転院して環境が変わることは大きな負担です。
転院先となる療養病棟では通常、積極的な治療が行われません。疼痛管理が主な医療であり、亡くなるのを待つばかりと感じられる病院もしばしば見られます。治らないまでも、例えばカテーテルを積極的に使えば、QOLを保てるケースがありますが、療養病棟ではそういった患者のためになる治療を積極的に選択する医師はあまりいないようにも思えます。
適切な対応があれば、残された日々を幸せに過ごせたにもかかわらず、医療制度によってその可能性を奪われている患者が非常にたくさんいるのです。

「医師の多忙」が引き起こす由々しき事態
近年、医療現場で深刻な問題と捉えられている出来事の一つに多剤耐性菌の多様化があります。
抗菌薬の開発は人類にとって大きな福音でした。それまで薬で治すことができなかった梅毒や淋病、結核などが治る病気になったのは抗菌剤が開発されたからこそです。1940年代にβラクタム系のペニシリンが大々的に使われるようになって以来、セフェム系、アミノ配糖体系やニューキノロン系など、さまざまな新しい抗菌薬が作られてきました。
一方、抗菌剤の開発と呼応するかのように出現してきたのが耐性菌です。特に最近では、多くの抗菌剤が効かない多剤耐性菌が登場しており、院内感染が大きな問題となっています。よく知られているMRSA感染症のほか、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性肺炎球菌、多剤耐性アシネトバクターなどがあり、薬が効きにくいため、いったん病院内で感染が広がると大きな被害が発生することがあります。
こういった治療が難しい多剤耐性菌が登場している背景には、抗菌剤の使いすぎや不適切な使い方があると私は考えます。高度急性期病院などで侵襲性の高い治療をする際、抵抗力の低下を見越して、患者には大量の抗菌剤を投与します。感染症を防ぐために必要な面はありますが、使いすぎると耐性菌が発生しやすくなります。
そのため、本来は使用量やタイミングについて、高度な判断が必要です。患者の様子をきめ細かくチェックして、使い方を調節しなければいけないのですが、時間に追われる医師にそんな余裕はありません。とりあえず大量投与で感染症だけは防ごう、と多くの医師が判断するため、多剤耐性菌の問題が深刻化しつつあるのです。
高度な医療技術があってもそれを使いこなせず、かえって院内感染により患者に害を与えてしまいかねない現状に、ジレンマを感じている医師は多いはずです。
佐藤 雅司
医療法人南労会紀和病院
理事長