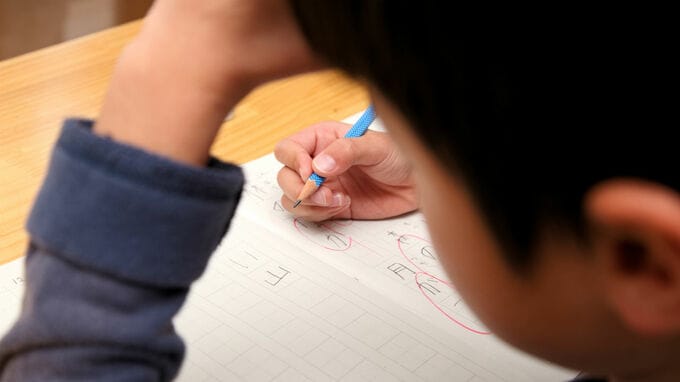教えるのではなく、子どもの頭を動かし続ける
大切なのは、どうすれば頭が動くのかを理解することです。このポイントを納得していただけたら、なぜ「わかるように教える」ことがダメなのかも了解いただけるのではないでしょうか。考えなくても「わかる」よう教えられていては、いつまで経っても子どもの頭は動きません。
頭を動かすキッカケは、疑問を持つことです。従って「なぜ?」「どうして?」がマジックワードになるのです。もしかすると日本では、「教師」という言葉が、多くの先生たちの呪縛となっているのではないかと危惧しています。
教師とは、教える師と書きます。『大辞泉』(小学館)には、その意味は「学校などで、学業・技芸を教える人。先生。教員」と記されています。
問題は「教える人」とある点です。これに日本人の好む「間違いを許さない気質」が加わるとどうなるか。例えば「原子力発電所は、事故など絶対に起こしてはならない。だから事故など100%起こらないように設計する」と考えれば、万が一、事故が起こった時の対応がよく練られていなかったり、シミュレーションがなされていなかったりします。その結果が、どうなったかを私たちは貴重な教訓として学びました。
学校の教師も同じではないでしょうか。教える人なのだから、万が一にも間違ってはいけない。きちんとわかりやすく教えることができなければならない、などと教師自身が思い込んでいるとどうなるか。
まじめな教師ほど、授業に備えて調べ物に時間をかけるでしょう。わかりやすく教えるために、あの手この手とできる限りの工夫を繰り出すはずです。子どもたちから質問されて、答えられないようなことがあっては絶対にならないと考えるのかもしれません。
そうした努力を重ねた結果が、わかりやすい授業となり、わかりやすいがために、子どもたちは何も考えずに聞いているだけになる。それが結局は考えない子どもを生み出しているのだとしたら、これほど皮肉なことはありません。
先生たちには、ぜひとも意識改革をしていただきたい。教師ではなく『考師』となるべきです。この言葉は私の造語ですが、要は子どもたちが考えるように仕向けて導く役を務めるのです。ですから考師自身が、最初から何もかもわかっている必要などまったくありません。もちろん、すべての教科、授業についてそうだというわけではなく、知識を伝える授業が必要なことは理解しています。
ただ、子どもと一緒に考え、子どもたちの考えを深めてあげる時間も大切にしてほしい。時にはそういう意識を持って、授業を行うことはできないでしょうか。
とにかく、どうすれば子どもたちが考えるようになるか。それだけにテーマを絞った授業をしてみる。子どもたちの集中力が途切れそうになった時には、まず励ましてあげる。考え抜けば最高の勉強になるのだから、もう少しがんばろうと考えることの大切さを語りかける。そうやって、もう一度考える気持ちを引き起こしてあげる。これが教師の役割だと考えれば、気の持ちようもずいぶんと変わってくるはずです。
食塩水の問題をどのように考えさせるか?
実際、私はそうしてきました。初めて食塩濃度の問題を考える時を例に、そのやり方を説明しましょう。
「3%の食塩水が100グラムあります」と問題文に書いてあれば、まず「%」の意味を子どもたちと一緒に考えるのです。これは「パーセント」と読む記号だけれど、どういう意味だろうかと問いかけます。この問いかけが、子どもたちの思考を引き起こします。
子どもたちは考え始めます。好き勝手にいろいろな意見を言うかもしれません。それらをまず全部受け入れます。
次に少しヒントを出します。「みんなも買い物をすることがあるから、消費税のことは知っているね。この間までは5%だった消費税が、今は8%になった。同じものを買う時に、消費税が5%と8%では、どちらがお金をたくさん払わないといけないかな。100円のアイスクリームを買う時、消費税が5%だったら、全部でいくら支払うことになると思う?」、こんな感じです。
あるいは「%」という記号そのものに注目してもいいでしょう。「%」をよく見て、バラバラにしてみたらどうなる、と尋ねます。「/」と「0」「0」が見えてくるね、と。「食塩水は、何でできているの?」「3%と20%なら、どっちの食塩水が塩辛いと思う?」「100点満点のテストで50点なら、マルの数はどれぐらいになる?」こんな質問を繰り返していると、子どもたちの頭は動き続けます。
このようにして子どもたちの頭を動かし続けることが、決定的に重要なのです。
この時、「考師」に求められるのは、自らが子どもたちと一緒に考え続けることです。自分が考えたことを口に出して、子どもたちに意見を求めることです。考えた結果が間違っていたとしても何も問題はありません。
頭を訓練する時に大切なのは、とにかく考え続けることであり、それは必ずしも正解に到達することだけを意味しません。正解に導くことよりも、考師が常に意識し続けるべきは、子どもたちを考えさせ続けることです。少し乱暴かもしれませんが、極端な話、答えなど出なくても問題ないのです。むしろ、答えは出ない方が良いといっても構わないほどです。なぜなら、正解にたどり着いてしまえば、その子どもには、それ以上考える対象がなくなるからです。
正解がどうでもいいなんて言うと、あまりにいい加減ではないかとお怒りになる方がおられるかもしれません。けれども、問題を解くことと、頭を使うことは別だということを、ぜひご理解いただきたいと思います。
そして頭を使えるようになれば、どんな問題でも、いずれ簡単に解けるように必ずなります。実際に頭の柔らかな子どもなら、灘中学校の入試問題でさえ1分ぐらいで解いてしまうのです。
頭の柔らかい子どもなら、問題文を読みながら、その意味を理解し、高速で試行錯誤していくでしょう。その結果、問題を読み終わった時には、ほぼ正解にたどり着いています。
問題文を読みながら、バラだと1個180円だけれど3個の袋詰めになると少し安くなる、それなのに10個入りだと1900円となるのは箱代が入っているからだ………[図表1]。
![[図表]思考授業の一例(小学4年生)](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/c/c/640/img_cccdc4b387378e544d9e837ec31240db502738.jpg)
頭を使えるようになるとは、こういうことを意味します。そのために必要なのは、このような問題の解き方を覚えることではなく、同じ問題を何度も練習することでもありません。解き方を理解することですらないのです。そんなことをいくら繰り返しても無意味です。頭を使う練習をひたすら繰り返す。それだけでよいのです。
そして、最低でも30分ぐらいは考え続けることが望ましい。5分ぐらい考えて、わからないから飽きたと放り出すようでは考える力は養えません。その意味では簡単には解けない算数の文章問題や図形問題などが、考える力を養うための良い教材となるのです。
江藤 宏
関西教育企画株式会社 灘学習院 学院長