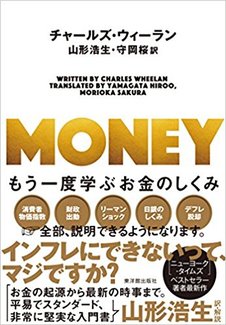アメリカの囚人たちは「サバ」をお金代わりに利用
アメリカで収監されている囚人たちは、現金の所有を認められていない。かわりにちょっとした物品を買える売店に掛け勘定口座を持つのが一般的だ。現金を流通させることなく、売店の商品を通貨として使える:切手帳、栄養補助食品のパワーバー、等々。過去の例にもれず、こういう商取引は、掛け勘定の統一単位について非公式の合意が形成されているとやりやすい。
第二次世界大戦中の捕虜収容所では、それがタバコだった。2004年に連邦刑務所での喫煙が禁じられて以来、アメリカの刑務所内取引の代表的な存在になったのが、パック入りのサバ、「マック」だ(※1)(缶詰でなくパック入りなのは、囚人たちが容器を鋭い凶器に加工して、刺し合いをしないようにするためだ)。サバのパックは持ち運べるし、保存がきく。
(※1)Justin Scheck, “Mackerel Economics in Prison Leads to Appreciation for Oily Fillets,” Wall Street Journal, October 2, 2008.
おかしなことに、サバは刑務所の外では、ディスカウント店でも人気がない。でも刑務所では、ツナ、カニ、鶏肉、牡蠣より売れ行きがいい──理由のひとつは、サバのパックは売店ではおよそ1ドルで販売されていて、マックを単位とするとドル計算がしやすいからだ。ドルやウォンとはちがって、サバには内在的価値がある。いつだって食べられるのだ。
もしも北朝鮮やアメリカの経済がサバでまわっていたら、最高指導者もFRBも、前回述べたような対応はできなかっただろう。最高指導者がテレビ放送に登場して、「サバがもはや無価値になった」とは言えない。サバはサバだ。冬用の外套と交換しようとしたら逮捕されるかもしれないけれど、地下に貯蔵しておけば、しばしば生じる飢饉の際には夕食にできる。価値があるものを無価値だと宣言はできない。政府がすべてのサバの没収を試みることはたしかにできるけれど、それはまったく別の作業だし、ずっとむずかしい課題だ。
同様に、アメリカのFRBが何も存在しないところに一瞬でサバのパックを数百万個生み出すことも不可能だ。FRBの窓のない部屋でボタンを押すと、シティバンクにサバが登場したりはしない。カチッ、カチッ、カチッ。この音ではサバは生まれない。
「米の引換券」と「米」、どちらを信じるか?
お金はどうしてこんなにヘンテコになったのだろうか。第一の、最も重要な洞察が、お金が富と同義ではないということだ。家は富だ。その中で暮らせるし、貸すこともできる。米一袋もやはり富だ。取引できるし、食べられるし、植えられるし、貯蔵しておいて後でこのどれかを実行することもできる。
でも米一袋は──家とはちがって──比較的均一な財なので、それが交換手段として潜在的に価値を持たせている。特に米が好きでなくても、支払いとして米一袋を受け取る場合もあるだろう。脂ののった魚が好きでなくても囚人たちがすすんでサバのパックで精算するように。
なぜかって? 米(あるいはサバ)を好む人は他にたくさんいるからだ。私にとって米に価値があるのは、他の人にとって米に価値があるからともいえる。これがさまざまな文化で歴史を通じて交換手段として使われてきたあらゆる財の重要な特徴だ:塩、黄金、タバコ、イルカの歯、ワンパム[筆者著書『MONEY』第8章を参照のこと]、動物の生皮。
すこし例を拡大してみよう。20キロ入り米袋が10個、地下室にあるとしよう。商取引の際に、この米袋を持ち歩きたくはない。そこで凝った証書を10枚作成して1枚ずつ署名して、証書と20キロ入り米袋の交換を約束する。1枚は、ゴルフのパットを教えてくれるゴルフプロに渡す。そして相手には、かれ本人でもだれでも、この証書を持った人ならいつでも地下室の米袋を引き取りに来てかまわないと伝える。これで紙幣のできあがりだ。商品(袋入りの米)に裏付けられた紙幣ではあるけれど。
そしてこの米の証書をもらったゴルフプロが、それを飼い犬の散歩係の女性への支払いに充てたら、流通紙幣のできあがりだ。だれであれ証書の持ち主が米を必要としたら、米と交換する。でなければ、証書は商取引に使われて、かなりの長期間、米袋は地下室に眠っていることになる。皮肉なのはこの点だ:米の証書の利用者たちの大部分は、いつでも引き換えできると確信しているかぎり、あわてて引き換えようとはしない。
でも米の証書の価値にわずかでも疑いが生じたら──それが正当な懸念であってもなくても──人々が証書をかざして玄関口に押し寄せて、米を要求するだろう。これは商品を基盤としたお金にかぎらず、もっと広範な金融システムの攪乱要因にもなりかねない。複雑きわまる金融システムの成功や失敗も、人々がどっちを信じているかに左右される。
Copyright Ⓒ 2016 by Charles wheelan All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form