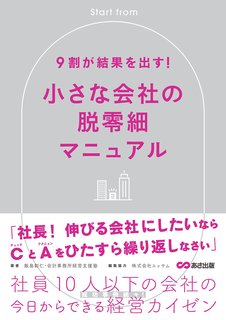今回は、企業における「家族経営」のメリットとデメリットを見ていきます。※本連載では、株式会社エッサム編集協力、株式会社古田経営・常務取締役の飯島彰仁氏、会計事務所経営支援塾の著書『9割が結果を出す! 小さな会社の脱零細マニュアル』(あさ出版)から一部を抜粋し、小さな会社が「脱零細企業」となるために必要な改善ポイントをレクチャーしていきます。
「意思決定の速さ」は大きなメリットだが…
ここまで説明してきたように、成長する会社へと変わるためにまず大事なのは、公私混同の状態を脱することです。そして、次に大事なのは家族経営を見直すことです。公私混同経営と家族経営。その二つの経営状態を改善してこそ、脱零細のスタートラインに立てると考えてください。
では、家族経営とはどのようなものでしょうか。
典型的な家族経営は、社長の奥さんが経理を担当し、お子さんが役員として営業部門を担当、あとは社員がいたとしてもパートやアルバイトを含めて数名といった状態での経営です。
その社員も、社長夫婦の友人や知人であったり、親族であったりすることもあるでしょう。ただ、どんな経営状態にも、メリットとデメリットがあるものです。家族経営についていえば、たいていのことを社長の一存で決めることができ、意思決定のスピードが速いということは大きなメリットです。また、家族経営で、社長の資産が一定程度あり、大きな商売にムリに手を出していなければ、他人から資本の提供を受けていないだけに、金融機関や取引先からの信頼も得られやすいといったメリットもあります。
そして何より、社長にとっては家族・親族という〝気心の知れた〟〝わがままのいいやすい〟人材を使って会社を経営できます。一言でいうと、「結束が固い」ことがメリットとなっているのです。
経営方針が行き違えば、近い間柄ほど「溝」が深まる⁉
ところが、そのメリットとデメリットは表裏一体です。経済が右肩上がりで、零細企業でも経済もしくは大手や中小企業の右肩上がりの動向についていけばよかった時代なら、メリットはそのままメリットとして発揮されます。意思決定がスピーディなら「あの下請は、注文に即応してくれる」と元請の評価は高まったでしょうし、社長が持つ資産の価値が上がれば、金融機関からの評価も得られやすいからです。
しかし、いまのままの家族経営を続けていける保証はありません。また、数年、数十年と家族経営を続けている社長は高齢化し、時代に即応した意思決定ができにくくなり、次代を担う人材もあまりいないというのが現状です。さらに、多様な考え方が浸透してきたいまは、業歴の浅い社長でも、結束の固いはずだった家族の経営の方向性が異なり始めると、それぞれが譲歩し合うことなく離反につながり、独立していくケースも見られます。とくに、会社を大きくしようとすると、家族間での方向性の違いが顕著になるようです。
経営方針について家族間で行き違い・仲違いが起きれば、近い間柄ほど溝が深まるのは、規模の大小にかかわらず、よく知られるところです。
そのような経営環境のなかで、家族経営を続けていくことはむずかしいと考えるのが小さな会社を経営する社長の実感ではないでしょうか。
苦境を脱するには、それこそ会社をたたむか、家族で固めていた〝やりやすさ〟を捨て去るのがベストな方法といえるでしょう。
望月経営会計事務所
経済産業省認定支援機関・経営コンサルタント・税理士
創業・ベンチャー支援センター埼玉 開業アドバイザー
平成20 年税理士登録後、望月経営会計事務所を開業。起業前から小さくても強い会社を作るコンサルティングを行い、起業前、起業後をトータルにサポート。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
税理士法人新日本経営
代表税理士
会計事務所及び事業再生コンサルティング会社に所属後、平成19年、新日本経営会計事務所開設。平成20年より埼玉県再生支援協議会専門アドバイザーとして活躍する。税理士法人新日本経営は、会計・税務はもちろんのこと、金融機関に強い税理士が、顧問先の「黒字化支援」、「融資・銀行対策」、「経営改善・事業承継」等の経営問題に積極的に取り組んでいる。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
西藤友美子税理士事務所
税理士・事務所所長
2002年、千葉県税理士会に税理士登録し、2005年、西藤友美子税理士事務所開設。事務所自ら、組織を活性化させ、経営を実践し①売上、②組織の成長を実現し、①未来会計、②資金調達支援、③経営コンサルで経営者のビジョンを実現。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
ちとせ会計事務所
所長税理士
平成6年4月クラヤ薬品(株)(現在の(株)メディセオ)に入社。病院・診療所営業担当(MS)として医薬品及び医療機器の販売を行う。平成8年6月税理士・不動産鑑定士事務所に入所。平成24年8月税理士・不動産鑑定士事務所の所長の死去により独立を決意、平成25年2月ちとせ会計事務所を開設し現在に至る。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
リアン総合事務所
税理士・キャッシュフローコーチ®・SP融資コンサルタント®
大学卒業後、信託銀行に就職したが、金融ビックバンによる銀行の再編成を機に退職。退職後、税理士だった祖父への憧れから会計事務所で働きながら税理士資格の取得に励む。
苦節18年の歳月を要したのち合格し、念願の独立を果たす。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
吉田一仁税理士事務所
ファイナンシャルコーチ®・税理士
大学卒業後、渋谷の大手会計事務所に4年半勤務し、税理士としての実務を積む。2005年1月、「吉田一仁税理士事務所」を開業。中小零細企業の社外CFO(財務幹部)として、「資金調達・資金繰りサポート」でお金を確保し、シンプルでわかりやすい「お金の見える化」でお金をコントロールし、成果の出る「経営コンサルティング」でお金を生み出すサポートをしつつ、経営者の意思決定を正しい方向に導くファイナンシャルコーチ®。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
株式会社エム・エス・コンサルティング/公認会計士・税理士山口学事務所
公認会計士・税理士・AFP
1981年11月~1987年12月 、プライス・ウォーターハウス公認会計士共同事務所および監査法人朝日新和会計社(現、あずさ監査法人)に勤務。1988年1月 、公認会計士・税理士山口学事務所を開設。経営者の夢を将来ビジョンとして明確にし、そこに至る道筋を経営計画としてまとめ、会計情報を経営に活かして、「脱・公私混同」+「中小企業版PDCA」でゴールを目指す。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
税理法人浜松合同会計わたなべ事務所
キャッシュフローコーチ ®・税理士
「数字だけ見ても分からない。思いだけでも社員は動いてくれない。」と悩む、中小企業の経営者、幹部の方に『お金のモヤモヤと、人のイライラをスッキリさせる、脱・ドンブリ経営のすすめ方』をアドバイス。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
飯田隆一郎税理士事務所
税理士
月次決算書と経営計画書、月次会議で、中小企業の社長を全力でサポートしている会計事務所。どうすれば利益が出て、お金が残るかを一緒に考え、毎月のチェックで計画と実績の差を確認し、対策を考え、社長の夢の実現をめざす。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
伊藤由美子税理士事務所
税理士・未来会計コンサルタント・経営計画コンサルタント
平成元年5月公認会計士事務所入所。平成7年12月税理士試験合格(税法:法人税、相続税、所得税)、平成8年8月税理士登録。平成9年4月税理士事務所開業平成9年7月TKC全国会入会。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
櫻井孝志税理士事務所
税理士
中小企業・零細企業や個人事業主のメリットは、歯車ではない、転勤がない、定年がない。デメリットは、収入が少ない、福利厚生がない、マニュアルや研修制度がない。働き甲斐のある仕事について、収入が付いてくればよいと考え、中小企業にふさわしいPDCAサイクルの回し方を指南。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
岡本剛税理士事務所
税理士・経営計画コンサルタント・PDCAコンサルタント
平成6年4月岩水明税理士事務所に入社。平成25年2月岡本剛税理士事務所開業。大阪市北区の南森町から経営をフルサポート。うまくいく会社・社長がいなくてもスタッフが自ら動く会社のPDCA(仕組み)を作りもサポート。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
竹内総合会計事務所
所長・税理士・中小企業診断士・行政書士
ヤンマーディーゼル(株)に入社し原価計算・経理業務に従事した後、大手会計事務所に入所し税務部長として中小企業の財務・税務・資金繰り指導に従事。
その後、平成9年マーケティング系コンサルタント会社に入社するとともに同年会計事務所を設立し所長に就任。平成15年1月、竹内総合会計事務所として独立。
経営サポート内容
経営診断による問題・課題の整理→経営計画による経営目標の策定→月次決算検討会による進捗確認→人事評価による全員経営の実現。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
金崎浩税理士事務所
税理士・行政書士・IT コーディネーター・ビジネスモデルデザイナー
1997年税務署退職、2002年税理士事務所を独立開業。いかにして未来に活力を与えられるかを念頭において、起業家の減少が歩止まりし増えていけるよう、経営者とともに進む。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル
加藤太一会計事務所
経営計画コンサルタント・公認会計士・税理士
代表の加藤太一氏が大手監査法人に勤務後、地元の北九州で開業。儲かる会社はどう動いているか、その様々な手法を、そのやり方をまだ知らない経営者に伝え、中小企業を元氣にすることを使命にサポート。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「脱零細企業」を実現するための「経営カイゼン」マニュアル