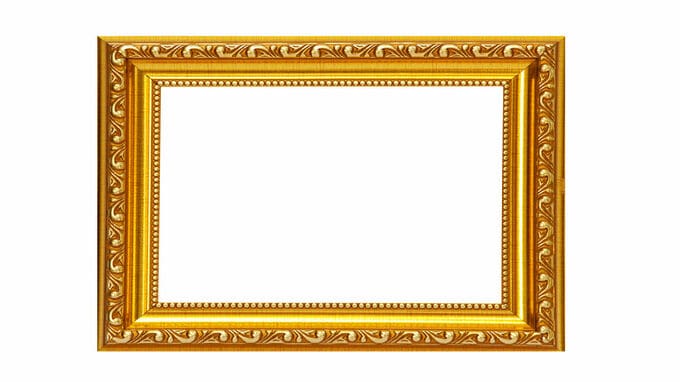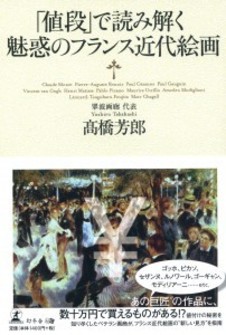写真の登場で「記録的な役割」を奪われた絵画だが・・・
前回の続きです。
では、セザンヌはなぜ後年に「近代絵画の父」と呼ばれることになったのでしょうか。その理由を探る前に、絵画とは何かを考えてみましょう。
かつて絵画とは視覚を記録するメディアでした。肖像画に象徴されるように、人には目で見えるものを自分の記憶の補助として、あるいは他人に見せるために記録しておきたいという欲望があります。そのためヨーロッパにおいては、見たものをそのまま描く写実的な絵画が発展しました。
しかし、19世紀になって写真が発明されると、目で見たものをそのままに記録する絵画の役割が奪われてしまいます。人が何時間もかけて手間をかけて描くよりも、カメラを使って光を平面に投影し、印画紙に感光するほうが簡単でコストがかからないからです。計算機が発明されて算盤が廃れてしまったのと同じことです。
こうして、目で見たものを一点透視図法で写実的に描く絵画は、その意味をだんだんと失っていきます。そこで新たに絵画に求められたのが、目で見たままではない美しさや芸術性でした。
もともと絵画においては、貴族の肖像画などで見られるように、しばしば理想化が行われていました。現代の芸能人のグラビア写真において、しわやしみが写らないように修正されるのが当たり前であるように、肖像画においては見た目よりも美しく、若々しく描くことが当然でした。
写真によって写実的な記録画の役割は奪われましたが、その代わり絵画には目で見たものに縛られずに自由に描くことが許されています。
写真の登場によって、絵画は作品として自立する方向へ進みだしたのです。
目指したのは、平面に再現する「三次元の現実」
その一つの帰結が、印象派でした。印象派は、人間の目で見たような精緻な造形をそのまま平面に写し取るのではなく、太陽の移動によって一瞬ごとに移り変わる光の反射や影の印象を粗いタッチで描くことで、躍動感や生命感を表現しました。
セザンヌは、印象派の代表であるモネの絵を評して「モネは一つの目にすぎない。しかし、何という目だろう!」と感嘆したといわれています。モネは、影が灰色ではなく、場合によっては紫に見えることや、光が白ではなく、さまざまな色のスペクトルであることを発見して絵画に表現しました。セザンヌはその目の能力に驚くとともに、物足りなさも感じていました。
なぜならば、目で見たものを平面に写し取るだけであれば、どんなに素晴らしい目を持っていたとしても本質的にはカメラと変わらないからです。セザンヌが目指したのは、絵画という二次元の平面の中に、いかにして三次元の現実を再現するかでした。カメラのように目で見たものをそのまま写し取るのではなく、絵画という枠のある二次元の平面が、それ自体で一つの作品であるべきだと考えたのです。
そのため、セザンヌは遅筆で知られています。67年の生涯で残した油絵の総数は、一説によれば954点です。22歳でパリに出てから本格的に絵を描き始めたと計算すると、45年間で1000点も描けませんでした。1年間でだいたい21枚程度しか描かなかった計算になります。
セザンヌの晩年に最初で最後となった個展を開催して積極的に支援した画商のアンブロワーズ・ヴォラールに対して、セザンヌは肖像画を描くことで感謝の気持ちを表現しました。
しかし、実際に描き始める前に素描(スケッチ)を何枚も描いたうえに、油絵を描き始めてからもしばしば筆を止めて何十分も考え込むセザンヌに、モデルとしてポーズをとっているヴォラールはだんだんと我慢ができなくなってきました。
なにしろセザンヌは1回で描き終わることなく、かれこれ100回以上もポーズを取らせたうえに、ヴォラールが居眠りして姿勢を崩した時には「リンゴは動かないぞ」と怒ったと伝えられています。
それくらいセザンヌは、キャンバスにおける絵の構築にこだわっていたのです。セザンヌは、一度描いた絵でも、満足できない仕上がりのものは破棄していたと言い伝えられています。そのため、現在にまで残っている絵の点数が少ないのかもしれません。