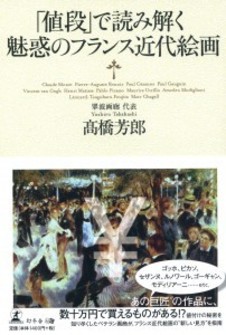幻覚や幻聴に苦しみながらもとりつづけた絵筆
幸いなことにゴッホの錯乱は一時的なもので、1月には退院を許されます。この時、ゴッホは親切にしてくれた若い医師レイに肖像画を描いて贈りますが、同居している医師の母親は〝狂人〞の描いた絵を気味悪がって、にわとり小屋の穴をふさぐのに使ったといわれています。村人のゴッホへの扱いは、その程度のものでしかありませんでした。
再びアルルで一人暮らしを始めたゴッホですが、2月には「毒を盛られている」「監視されている」などの幻覚や妄想が激しくなり、病院に収容されます。以後、村人の反対もあってゴッホは二度とゴーギャンとともに暮らしたアルルの黄色い家に戻ることができませんでした。
タイミングが悪いことに、テオは4月の結婚式と新居への引っ越しを控えており、忙しい状況でした。ゴッホはテオに見捨てられるのではないかという恐怖と、これ以上テオに迷惑はかけられないという思いから、自ら精神病院に入ることを希望します。そして1889年5月、テオがパリで結婚式を挙げたすぐ後に、ゴッホはアルル近郊のサン=レミの精神病院へと移ります。
この病院の中での生活は、1890年の5月まで1年間続きました。幻覚や幻聴の発作がたびたび起きてゴッホを苦しめましたが、絵を描くことはやめませんでした。もはや、ゴッホにはそれしか残されていなかったからです。
オランダに行けば必ず立ち寄るゴッホ美術館ですが、私が初めて訪れたのは大学時代のことでした。図版で見るのとは違う本物の作品に感激したものです。
ゴッホは、私の父も好きで画集を持っていたので、子どもの頃から馴染みのある画家でした。
初めて行くゴッホ美術館には、家にあった画集に掲載されていて見慣れた作品もありましたが、そのうちに、初めて見る1枚の作品に目が留まりました。
花が咲く木の枝を見上げて描いた単純な構図の絵でしたが、他の作品にはないオーラを放っていて、何かを訴えてくるのを感じました。
その絵に魅せられてしばらく見とれていると、そこはかとない喜びに満ちた幸福感が湧きあがってきました。
それが『花咲くアーモンドの木の枝』でした。
後日、知ったところでは、1890年、兄弟の絆を超えた人生の同志ともいえる弟テオに長男が生まれた時、それを知ったゴッホが喜び勇んで描き、甥の誕生祝いに持参した絵だとわかりました。ちなみに、テオはその長男に、兄と同じフィンセントという名前を与えています。
『花咲くアーモンドの木の枝』は、一見ゴッホの絵のように見えません。よく見ると枝などにゴッホの筆致が見えるのですが、まるでゴッホの愛した日本画のような繊細なタッチで丁寧に花が描かれています。
ゴッホはテオへの手紙で「この作品は今までで一番根気よく、一番冷静な気持ちで、一番上手に描いたものだ」と伝えています。
短い生涯の最後、ようやく評価されるようになった絵画
この絵を描いていた2月、ゴッホの評価はだんだんと上がり始めていました。美術評論家が雑誌でゴッホの作品を絶賛したほか、テオからも絵が売れたとの報告が入りました。しかし、ゴッホに残された時間はわずかでした。
1890年4月、チューブ絵具を絞って飲んで死にかけたゴッホは、精神病院に居続けることにも苦しさを感じて、外に出してくれとテオに頼みます。
5月、テオはゴッホを退院させて、ピサロの紹介で知った絵画コレクターの医師ガシェに兄を預けます。
ガシェ医師のもとで一人暮らしを始めたゴッホでしたが、7月には拳銃で自分の胸を撃って、37歳の短い生涯を閉じます。
ゴッホが亡くなった半年後の1891年1月、兄を支え続けた弟テオも病気で後を追います。33歳でした。
ゴーギャンがタヒチで世を去るのは、ゴッホの死から13年が経った1903年です。亡くなる2年前には、わざわざヨーロッパからひまわりの種を取り寄せて育てて、友を偲ぶ『肘掛け椅子のひまわり』を描いています。
ゴッホの生涯はあまりにもドラマチックであるために、しばしば物語的な側面ばかりに光が当てられます。たしかに、ゴッホの精神病院入院や自殺がなかったとしたら、その絵の金銭的価値はこれほどまでに高くならなかったかもしれません。しかし、そのストーリーがなかったとしても、ゴッホの作品は魅力的であり、芸術としての本質的価値を持っています。ぜひ一度、本物に触れていただきたいと思います。