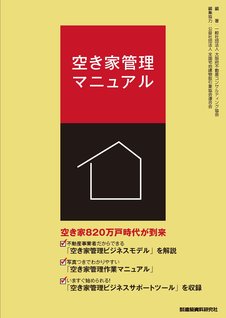今回は、具体的な空き家管理のうち、建物を長持ちさせるポイントを見ていきます。※本連載は、一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会(会長・米田淳氏、理事・井勢敦史氏・岡原隆裕氏、会員・芳本雄介氏/他)の編著、『空き家管理マニュアル』(建築資料研究社)の中から一部を抜粋し、近年深刻化する空き家問題について、その「管理」の具体的なポイントをご紹介します。
単に通気・換気するだけでは結露対策の効果は出ない
前回に引き続き、空き家管理の建物管理について見ていきます。
③建物を長持ちさせる(財産的価値をできる限り下げない)ためのポイントとその他予防措置
ⅰ)通気・換気
通気や換気などをせずに空き家を放置しますと、結露などによる湿気により建物が傷んだり、カビが生えてそこにシロアリが発生したりすることがあります。
なお、結露が発生するメカニズムは夏と冬とで異なり、建物の構造や部材によっても結露対策は異なります。通気・換気をすることによって結露対策効果が必ずしも発揮されるのではなく、季節や時刻によって変化する環境などに応じた通気・換気方法を採る必要があります。
例えば、夏場のように高温多湿の時期では、日中は換気口を閉じておき、陽が落ちて外気の湿度が下がってから風を通すのが良いとされています。一方、人手に頼らない方法として、換気扇を活用することが考えられますが、換気扇による連続換気は降雨時に室内に湿気を取り込むことになるため逆効果です。
このように、結露の発生を抑える簡単で確実な方法は、屋内外の空気を入れ替える換気ですが、室内に湿気を取り込まないようにし、除湿効果のあるときだけ換気を実施するのは、状況に応じて頻繁に対応することになり、実際に困難であることを認識しておく必要があるでしょう。
排水トラップには時々水を流し、その後は塞いでおく
ⅱ)給湯器の凍結予防
Ⓐ一般的な給湯器本体には、凍結予防のヒーターが付いているため、給湯器に通電しておきます。
Ⓑ給湯器が貯湯タンク式のものは水抜きをします。また、配管の排水も行います(取扱説明書を参照する)。
Ⓒ気温が氷点下に下がることが予想される場合は、水を少しずつ流しておきます。
ⅲ)浄化槽への対処
浄化槽内のバクテリアにブロアーで空気を送り込むため、空き家にするときも通電しておくことが基本になります。また、届出や法定点検、維持管理などもが関係するので、専門業者に対応策を相談しましょう。
ⅳ)排水口の悪臭予防
排水トラップの水が蒸発してなくなりますと、封水が切れて臭いが上がってきたり害虫が侵入したりする恐れがありますので、時々水を流し、その後の蒸発量を少なくするため、ゴム栓がついている箇所(洗面・浴室)などはラップでゴム栓を包んで栓をし、それ以外のところはテープで塞いでおきます。
ⅴ)和室の畳床湿気予防
湿気の予防のため、マンション、戸建てにかかわらず、畳はあげておきます。畳が日焼けで変色するからと表面を新聞紙などでおおうのは、余計に湿気がこもりますので避けます。
ⅵ)建物
Ⓐ外壁のひび割れ、設備の水漏れ(水道を止めていない場合)、雨漏りなどを確認します。
Ⓑ屋内外の水染みをチェックします。特に屋外バルコニーの軒裏など、モルタルの落下につながるおそれのある部分を確認します。
Ⓒバルコニー手すりに笠木がある場合、隙間の有無を確認します。
Ⓓ樋やバルコニー排水口の異物(枯れ葉やボールなど)の詰まりを確認します。
ⅶ)庭
Ⓐ木の切れ端などが落ちていれば処分します。シロアリがそこにすみつき、建物に移動する場合があります。
Ⓑ草刈りや植栽の剪定、落ち葉や投棄物の処分を行います。
建物管理のチェックポイントは、居住者が高齢化するなどして目が行き届かなくなった場合や手が回らなくなった場合などを除き、居住することによって自ずと確認し、解消できるポイントです。
しかし、このような居住している状態と同程度のレベルを空き家管理によって達成しようとするのは現実的ではなく、依頼者の期待する管理の目的とその管理に要するコストを比較検討するなどして、必要な空き家管理のレベルを決定することになります。
一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 会長
大丸ハウス株式会社 代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、二級建築士
大阪大学基礎工学部卒。きりう不動産信託株式会社顧問、一般社団法人全国不動産コンサルティング協会専務理事、一般社団法人全国空き家相談士協会専務理事。平成27年12月より大阪市空家等対策協議会委員。
【主な著書・寄稿等】
著書:『新・不動産信託の活用術』(住宅新報社、2008年)、『不動産の信託』(共著、住宅新報社、2005年)
寄稿:『地代・家賃と借地借家』(住宅新報社、2014年)、『事例でわかる!コンサルティングによる不動産ビジネス』(週刊住宅新聞社、2012年)
解説・監修:『不動産コンサル過去問題集』(住宅新報社、2006年~2017年毎年)、事例提供/『居住福祉産業への挑戦』(東信堂、2013年)、『実例にみる信託の法務・税務と契約書式』(日本加除出版、2011年)など
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載空き家820万戸時代が到来――空き家を持つ人のための管理マニュアル
一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 理事
公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、公認ホームインスペクター、ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、木材アドバイザー
司法書士事務所・不動産コンサルティング会社を経て、現在「住生活コンサルタント」として活躍。
誰もが安全・安心・健康で快適な住生活を営むことができる環境形成を目指し、不動産流通市場の透明化に関する仕組みづくりや地域の活性化、空き家問題などに精力的に取り組む。
また「第三者の立場」で消費者向け、事業者向けの講演・研修・コンサルティングで全国を飛び回る傍ら、業界紙等への執筆も行う。
現在、「新建ハウジングプラスワン」において「小さな工務店のストックビジネス最前線」を連載中。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載空き家820万戸時代が到来――空き家を持つ人のための管理マニュアル
一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 理事
株式会社つばさ資産パートナーズ 代表取締役
公認不動産業務コンサルティングマスター、相続対策専門士、宅地建物取引士、CPM®(米国不動産経営管理士)、賃貸不動産経営管理士
立命館大学法学部法律学科卒。不動産相続コンサルティングを皮切りに、不動産業務、相続サポート業務を行っている。相続に強い専門家ネットワークを構築しているのも強み。
空き家解消の取組みとして一括賃料前払いサブリース方式を使い、空き家活用や空き家の買取り、デザイナーズ戸建賃貸を新築する投資事業などにも取り組んでいる。不動産オーナー向け勉強会「つばさ資産塾」を主宰。
【講演歴】クレオ大阪西(大阪市立男女共同参画センター)、大阪市立住まい情報センター、岡山リビング新聞社、ほか多数。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載空き家820万戸時代が到来――空き家を持つ人のための管理マニュアル
一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 会員
株式会社プロブレーン 代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士
「思いを築く不動産のCreative Company」をモットーとし、モノだけではなくお客様の思いにもフォーカスし不動産の困りごとを解決します。心豊かな暮らしを育むために和やかに家系学を学ぶ、「幸運を拓く 家族の法則」講座を主催。
【得意分野】①コンサルティング事業(不動産運用、賃貸経営、空き家、相続、信託、債務整理)②不動産再生事業(空き家の借上、老朽アパートの引取り、借地権付建物の引取り)③仲介事業・売買事業(土地、住宅、収益マンション、収益ビルの仲介・売買)
【寄稿】『地代・家賃と借地借家』(住宅新報社、2014年)、『事例でわかる!コンサルティングによる不動産ビジネス』(週刊住宅新聞社、2012年)
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載空き家820万戸時代が到来――空き家を持つ人のための管理マニュアル