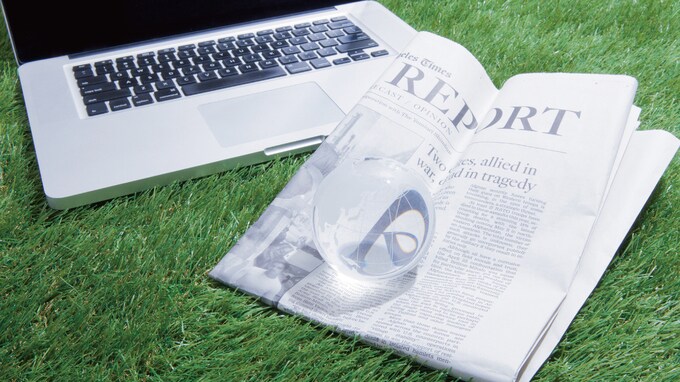日銀に手厳しかったWSJの社説
一方、海外のメディアでは、アメリカを代表するウォールストリートジャーナル紙が、翌日の社説で「日銀の補完策政治的で信頼を失う」と手厳しかった。
2014年に黒田総裁は、
「日本のインフレが1%を切ることは、自分の人生のなかではない」
とさえ断言していた。
海外メディアの見解に添って市場も動いた!?
だが、そうではなかった。すぐに同紙は、
「日銀のバランスシートの拡張規模は、FRBの比ではないほどに過激である」
と忠告した。また、
「インフレ目標が今後2年程度で達成するめどはほどんどなく、黒田日銀がさらに大きな資産購入を実施する圧力が増大し、それは一段の円安につながり、アメリカや中国、その他の貿易相手国との緊張が高まるだろう」
と批判した。さらに、
「日銀の補完策は、ビジネスの意思決定に政治が介入する懸念を高める」
として、賃金引き上げや設備投資に協力する企業を支援するため、政府の圧力のもとで日銀がETFを購入するやり方を批判した。
「企業のガバナンスや利益は企業自身が決定すべきであり、そのような経済政策は混乱しているように見える」
「中央銀行の力を政府の政治的な目的を促進するために使うことは、資源の非効率な配分につながり、成長を阻害し、また日銀の独立性を損なう」
と厳しく批判した。そして、
「日本企業は日本経済の遅い成長力のために、借り入れや投資をしない」
「安倍政権が再び競争促進的な規制緩和と租税改革をしないのであれば、金融政策ができることは限られている」
と主張し、最後に、
「日銀ではなく安倍首相に日本の経済の運命は託されている」
と結んだ。これらはきわめて妥当な見解だと評価できる。実際に市場も、その後のウォールストリートジャーナル紙の社説の見解に添って動いていったかに見える。