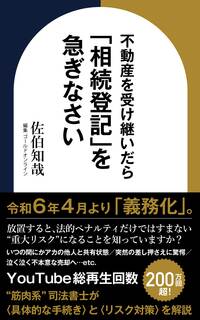落とし穴①:内容は正しくても「書き方」が間違っている
遺言書で最も多いトラブルは、内容そのものよりも「書き方」「形式の誤り」です。これが間違っていると、せっかく残した遺言も無効となり、想定した効力が得られなくなってしまいます。
<よくあるミス>
●相続人の「名前のみ」を書いた
●不動産の表記を「自宅」とだけ書いた
●預金を「〇〇銀行の口座」とした
●遺言書の最後に日付を入れ忘れた
これらはすべて、法務局・銀行など相続手続きでは受け付けられない可能性があります。
相続人の名前のみだと、同姓同名の他人への相続の意図で書いた可能性をなくすことはできませんし、不動産は、登記事項証明書に記載されているとおり「地番」「家屋番号」などによる特定が必要です。
遺言書にこういった記載がないと、遺言書で相続人や不動産の特定ができないため、「遺産相続の手続きができません」という事態になります。実際、「父が遺言書を残してくれました!」と誇らしげに持って来られた遺言書が、内容は立派でも不動産の書き方が「自宅」だけで、一切特定できないというケースは少なくありません。
結果、遺言書がないのと同じ状態になり、相続人全員からの合意書類(遺産分割協議書)が必要となり、そこから初めて揉め始めるのです。
落とし穴②:受け取る側の「感情を逆撫で」する記述内容
遺言書の内容が法律上正しくても、家族の「感情」に火をつけてしまうケースがあります。たとえば、
<事例>
母親が亡くなり、遺言書には「長男に自宅不動産と預貯金を相続させる。次男には100万円を渡す。」と書かれていた。
母親の自由意思に基づき作成された遺言書なので、法律的にはなんの問題もありません。しかし、次男からすれば、内容に納得できない可能性が高いでしょう。
内容を見ただけで「オレは軽んじられていたのか?」「そんなふうに考えていたのか」と思うでしょうし、ましてやそこに「母の介護はほとんどオレがやっていたのに」「兄は家族と仲が悪かったのに」といった事情が絡めばなおさらです。法律と気持ちの問題はまったく別です。この「感情のこじれ」が起これば、相続手続きは長期化します。
さらに危険なのが「遺留分」です。遺言書で財産のすべてもしくはほとんどをだれか1人に渡すよう書いてしまうと、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)が発生します。
「親の意思だから」と言っても、遺留分は強い権利です。請求された瞬間、手続きは止まり、相続人同士の関係が破綻してしまうことも多くあります。
落とし穴③:「余計な付言事項」がトラブルを加速させる
多くの方が、遺言書の最後に「付言事項」という「思いのメッセージ」を書きます。法的拘束力はありませんが、家族に向けたメッセージとしては非常によいものです。
しかし実務では、この付言事項が原因で「大揉め」するケースが驚くほど多いのです。
<典型的な“危険な付言”の例>
「長男は昔から親不孝だったので、一切の財産を渡さない」
「次男の嫁には一切関わってほしくない」
「長女は母親に冷たかった」
「絶対にこの家を売ってはならない」
「〇〇家を絶やすな」
こうした内容は、読む側の感情を強烈に刺激します。結果として、
●「なぜこんなことが書かれたのか」という真意を巡る争い
●遺言の有効性そのものへの疑い
●兄弟姉妹間の長年の遺恨の再燃
●妻・夫など「相続人ではない家族」の怒りに火がつく
●遺留分侵害額請求が加速
など、相続手続きが泥沼化します。
とくに「この家は守ってほしい」「売るな」という付言はトラブルの火種になりやすいので要注意です。不動産は、相続人の平等な相続や、相続税の納税資金のために売却・換価する必要が生じるケースが多々あります。そのため「売るな」と書かれていることで、相続人たちが身動きできなくなることもあります。
もちろん、付言事項は本来とてもよい仕組みです。しかし書き方を誤ると、家族の心に刺さる「負のメッセージ」に変わるという点は、よく理解しておく必要があります。
落とし穴④:後から「遺言者の認知機能」が争点になる
遺言書は書けたとしても、書いた時点の判断能力が問題になるケースが急増しています。とくに下記のようなケースは、相続人の一部が「判断能力がなかったのでは?」と疑い、主張する典型的なポイントになります。
●文字がひどく震えている
●内容が飛び飛びになっている
●作成日と医療記録に残された認知症の診断が近い
●施設入居後に作られた遺言書である
遺言書の内容を巡って争いとなった場合、遺言書はあとから「能力の証明」が問われることになります。そのため、本来は事前に医師の診断書を取っておく、公証人や専門家に関与してもらうことが望ましいのですが、一般の方はそのリスクを知らずに作ってしまいがちなのです。
落とし穴⑤:前妻の子がいる相続で遺言書が「火種」に
父が再婚し、前妻との子どもがいるケースも、遺言書が「相続トラブルの地雷」となりがちです。
●前妻子は疎遠で連絡が取れない
●後妻が大半をもらう内容に、先妻の子どもの怒りが爆発
●先妻の子どもによる遺留分請求で後妻が精神的に追い詰められる
いくら遺言書に「全財産を後妻とその子に」と書き残しても、法的に前妻の子どもも相続人ですので無視することはできません。
また、遺言書がきっかけで「存在すら知らなかった異母きょうだい」が名乗りを上げるケースも珍しくありません。
落とし穴⑥:専門家による「詰めの甘い遺言書」が揉めごとの元に
遺言書は作る人によって完成度が大きく違います。そして問題となるのは、下記のようなケースです。
●不動産の特定が甘い
●相続税のことをしっかり考えていない
●二次相続を想定していない
●遺留分侵害に気づいていない
●死亡後の不動産売却の設計がない
●家族関係の「感情」がまったく読めていない
これらは書面としては問題なく見えても、実務で機能しなくなることが多々あります。とくに金融機関の高額な遺言信託でも、意外なほど内容が薄いケースは本当に多く、相続開始後に「こんなはずではなかった…」という相談が続出します。
遺言書は、書き方を誤れば「家族関係を破壊する時限爆弾」に
遺言書は本来、家族への思いやりから生まれるものです。しかし、書き方を誤ると、家族を深く傷つける元凶になります。とくに、
●財産の特定
●遺言者の認知機能
●家族間の感情のこじれ
●遺留分への配慮
●再婚・前妻の子への認識と配慮
●依頼する専門家の熟練度
●「付言事項」の書き方
これらの1つでも誤れば、遺言書は機能しません。むしろ「書いたせいで、逆に問題が大きくなる」ことすらあるのです。遺言書は「書けば終わり」ではありません。「家族の未来を見据えた設計こそが、遺言書の本来の姿」。これが相続実務の真実なのです。
佐伯 知哉
司法書士法人さえき事務所 所長
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<