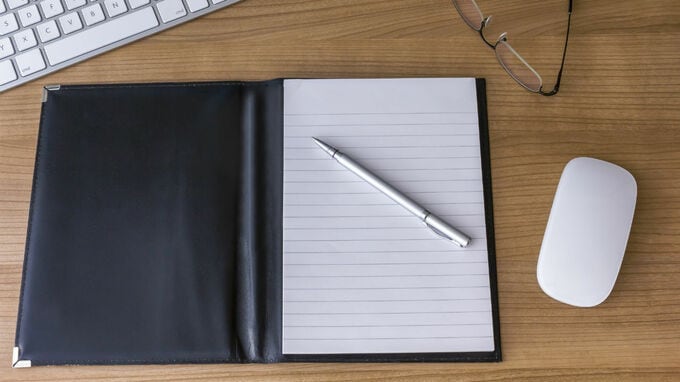一般財団法人の設立者は「法人」でも可能
一般財団法人の設立の場合は、設立者(財産を拠出して法人を設立する者)が主導して行います。設立者には、法人もなることができます。設立時に拠出する財産は、300万円以上となっています。具体的な設立の流れは次の通りです。
〈手順①〉設立者が定款を作成し、公証人の認証を受ける。
定款には、以下のような事項を記載します。
●目的
●名称
●主たる事務所の所在地
●設立者の氏名または名称および住所
●設立に際して各設立者が拠出をする財産およびその価額
●設立時評議員、設立時理事および設立時監事の選任に関する事項
●設立時会計監査人の選任に関する事項
●評議員の選任および解任の方法
●公告方法
●事業年度
なお、次のような事項は、定款に記載しても効力を有しません。
●設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
●法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
●評議員を理事または理事会が選任し、または解任する旨の定め
〈手順②〉設立者が財産の拠出の履行をする。
〈手順③〉設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含む)の選任を行う。
〈手順④〉設立時理事および設立時監事が設立手続きの調査をする。
〈手順⑤〉設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に設立の登記の申請を行う。
遺言によっても設立できる一般財団法人
一般財団法人は、遺言によっても設立することができます。相続税対策としての法人化は、通常、生前に行うことになるでしょうが、財産の一部等を自らの死後、特定の目的のために財団法人の形にしておきたいと考えている人もいるかもしれません。参考までに、遺言による設立の流れについても触れておきましょう。
〈手順①〉設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を示し、定款に記載すべき内容を定める。
〈手順②〉遺言執行者が遺言の執行をする。遺言に基づいて遅滞なく定款を作成し、公証人の認証を受ける。
〈手順③〉遺言執行者が財産の拠出の履行をする。
〈手順④〉定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含む)を定めなかったときは、これらの者の選任を行う。
〈手順⑤〉設立時、理事および設立時監事が設立手続きの調査をする。
〈手順⑥〉設立時、理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に設立の登記の申請を行う。