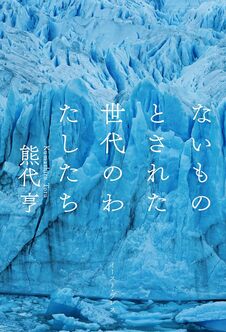足元で進行していた「激動」
ベルリンの壁崩壊やソビエト連邦の解体が相次いだこともあり、この頃の大人たちは「激動の時代」という言葉を連呼していた。冷戦終結が大きな出来事だったこと、それ自体は否定できない。だが他にも、激動と呼ぶべき変化が私たちの足元で進行していたのではなかっただろうか。ひとつには、バブル景気の崩壊というかたちで。もうひとつは、田中が描いてみせた超─先進国的なライフスタイルが全国に定着することによって。
今日では、バブル景気の終わりは1991年だったとみなされている。しかしテレビでは『東京ラブストーリー』『101回目のプロポーズ』といったトレンディドラマが高視聴率をキープし、KAN「愛は勝つ」や大事MANブラザーズバンド「それが大事」といった楽天的な流行歌がオリコンチャート1位を獲得していた。
バブル景気の代名詞とみなされがちなディスコ「ジュリアナ東京」も、実際には景気後退期にあたる1991年から1994年に営業している。地方の女子高生までもがブランドバッグを持ち歩くようになり、財をなした資産家が故郷に錦を飾るように大仏を建立する社会風潮のなかで、長く続く退潮の時代を見抜いていた人はほとんどいなかった。少子高齢化についても同様だ。当時、大半の人々が認識していたのは少子化ではなく、1972年に発表されたローマクラブ『成長の限界』や1974年に開催された「第1回人口会議」に象徴される、人口爆発ではなかったか。
経済的繁栄に浮かれる者は石川県にもいた。
1987年、故郷に錦を飾りたい石川県出身の会社経営者によって、加賀大観音という巨大な仏像が建てられ、「ユートピア加賀の郷」というテーマパークが開業した。地元の人々からははじめから酷評され、「じきに倒産する」と噂されていたが、案の定、21世紀を待たずに閉園となった。今日では訪れる人も稀で、倒壊などの危険から、バブル期の負の遺産として言及されることが多い。
熊代 亨
精神科医