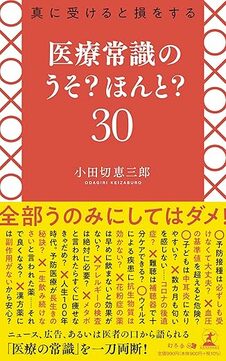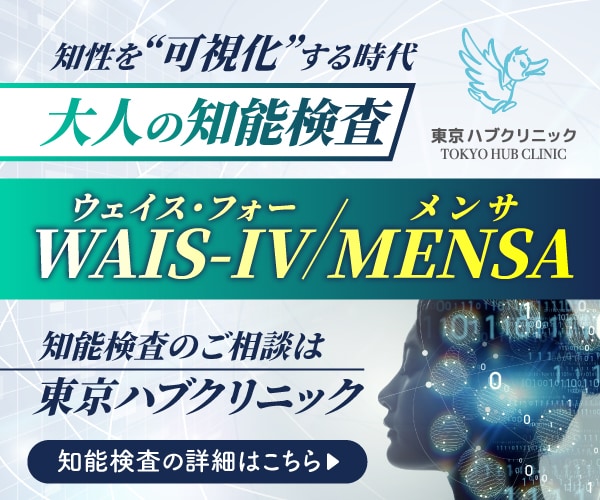花粉症の仕組み
お正月が明けた頃から「スギ花粉症の薬を処方してください」と来院する人がいます。どうやら花粉症の薬は症状が出ていなくても早めに服薬を始めたほうが効果的と、テレビやインターネットでアナウンスされているようです。
これについては、そこまでしないといけないような重症な人は多くないと思うけどなあ、たいていの人は症状をみながら飲むのでいいと思うけどなあ、と思っています。
基本的に花粉症は、花粉などアレルゲンに触れた直後15分以内に起こるといわれ、くしゃみ、鼻水を中心とする急性相、その後安定期のような時間があり、数時間後に現れる鼻詰まりを中心とする遅発相があるといわれています。一回の花粉(アレルゲンの暴露)ならそれで終わり、翌日は何もないということになりますが、花粉症の季節は、空を覆う大量の花粉が飛んできます。連日の花粉の暴露で急性相と遅発相が同時に来るようになってしまいます。
花粉症の薬はなぜアレルギーを抑えられるの?
花粉症で処方される薬は、アレルギーが発症する経路をブロックする目的で使われます。花粉症が発症する仕組みを簡単に説明しておくと、空気中を飛んでいる花粉が鼻や口から入り、体内の免疫システムが花粉を「アレルゲン」と察知すると、闘うための物質「IgE抗体」が作られます。花粉が体内に入ってくるたびに抗体が作られるので徐々に蓄積し、一定量に達するとアレルギー反応を起こすようになります。
よく、コップの水があふれてアレルギーが発症すると例えられますが、コップに溜まっていく物質がIgE抗体というわけです。アレルギー反応が起きると、ヒスタミン、ロイコトリエン、トロンボキサン、PAFなどの化学物質が放出されるのですが、その際に神経や粘膜が刺激されて、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりなどが起こります。
そこで刺激になってしまう化学物質の作用を抑えるのが花粉症の薬です。急性相の主役のヒスタミンを抑える「抗ヒスタミン薬」、主に遅発相に効果を発揮する「抗ロイコトリエン」などの薬が花粉症の代表的な薬です。何十年も前に開発された初期の抗ヒスタミン薬もそうですが、抗ヒスタミン薬は効果が比較的早く出ますし、近年発売されているものは眠気や口の渇きといった副作用もかなり抑えられています。
鼻の中に直接噴霧する点鼻薬も効果がある人には効果が得られます。血管収縮効果のある点鼻薬は、噴霧してすぐに鼻詰まり改善の効果が得られます。鼻の中の粘膜は毛細血管がたくさんあるので効果が出やすいのです。しかしこれは使いすぎると治りにくい鼻詰まりになるといわれているので、私は積極的には使っていません。