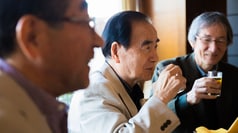「養育費の支払義務」とは?
そもそも、親はなぜ子どもの養育費を払わねばならないのでしょうか? まずは、法的根拠がどこにあるのか、具体的にはどういった義務内容となっているのか確認しましょう。
養育費は、親が子どもを「扶養すべき義務」の一種です。民法877条1項は、親子や兄弟姉妹が互いに扶養し合う義務を定めています。
(扶養義務者)第877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
親である以上、離れて暮らしていても子どもの養育費を負担しなければなりません。養育費の支払義務は、子どもに自分と同等の生活をさせなければならない「生活保持義務」です。親は、自分の生活レベルを落としてでも、子どもに自分と同等の生活をさせなければなりません。
養育費の支払期間
養育費は、いつまで支払うべきなのでしょうか? ここでは、養育費の支払い時期について解説していきましょう。
養育費は夫婦で取り決めた期間まで支払う
養育費の支払い終期は、夫婦間で取り決めをした場合は、その時期までです。たとえば、「20歳の誕生月まで」や「22歳の誕生月まで」などと年齢で取り決める場合もあれば、「高校を卒業する月まで」や「大学を卒業する月まで」などと卒業時期で取り決める場合もあるでしょう。
養育費の終期を「成人」と定めた場合
2022年4月1日から、民法の改正により、成人年齢が引き下げられました。これにより、従来は20歳であった成人年齢が、18歳となっています。
では、養育費の終期について「成人する月まで」などと取り決めていた場合には、どうなるのでしょうか?
まず、2022年4月1日以降に取り決めをした場合には、18歳の誕生月までと解釈されるでしょう。ただし、これから養育費について取り決めをする際には疑義を生じさせないためにも、「18歳の誕生月まで」などとより具体的に定めておくことをおすすめします。
一方、2022年3月31日以前に養育費について「成人する月まで」と取り決めた場合には、20歳の誕生月までと解釈されるでしょう。改正前に「成人する月まで」と取り決めたのであれば、少なくともその時点においては、双方ともに「20歳の誕生月まで」との認識であった可能性が高いためです(参考:法務省:成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について)。
注目のセミナー情報
【資産運用】5月9日(金)開催
初期投資1,300万円・想定利回り16%!
安定収益、短期償却、社会貢献を実現する
「ビジネスホテル型トレーラーハウス」
待望の新規案件発表!
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資