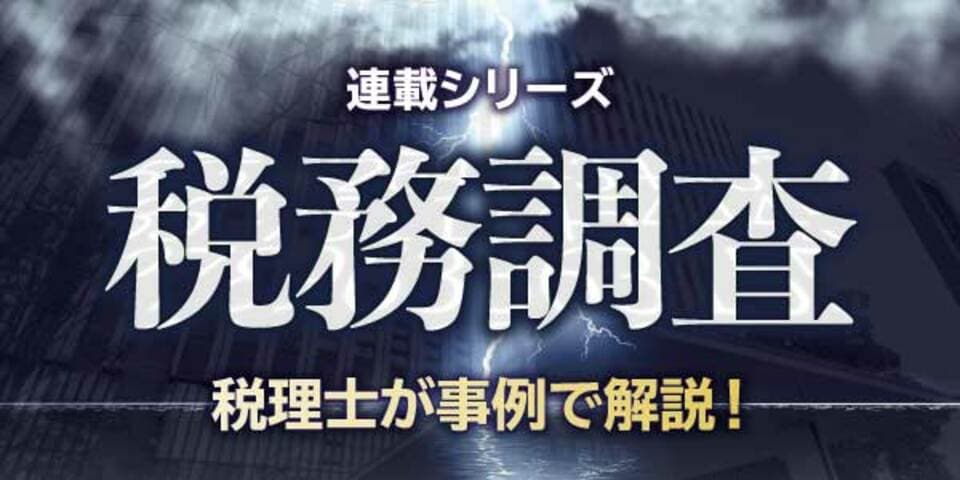「相続時精算課税制度」の活用も有効
いかがだったでしょうか? 毎年110万円以下の贈与であれば生前贈与として相続税の負担が少なくなるということは広く知られていますが、贈与の実態がない場合は、税務調査の際に否認されて追徴税額を徴収されることとなるため注意が必要です。
また、税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びるという改正が行われました。一方で、2023年までは、相続時精算課税制度について、一度選択した後は少額でも贈与税額の申告が必要だったのが、2024年1月からは年間110万円の非課税枠が設けられ、110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる改正が行われました。
この改正によって相続時精算課税の使い勝手が良くなり、有利な場合も増える可能性がでてきたため、今後は相続時精算課税制度を利用する人が増えるかもしれません。
誤った生前贈与を行った結果、苦労するのは遺された家族です。家族に迷惑をかけないためにも、実際に生前贈与を行う際は、専門家等によく相談するなどして慎重に検討しましょう。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/17開催】日本株長期上昇トレンドの到来!
スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資
【2/18開催】
金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険
“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察
「これからの不動産投資」
【2/18開催】
認知症となった80代賃貸不動産オーナー
家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!
『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは