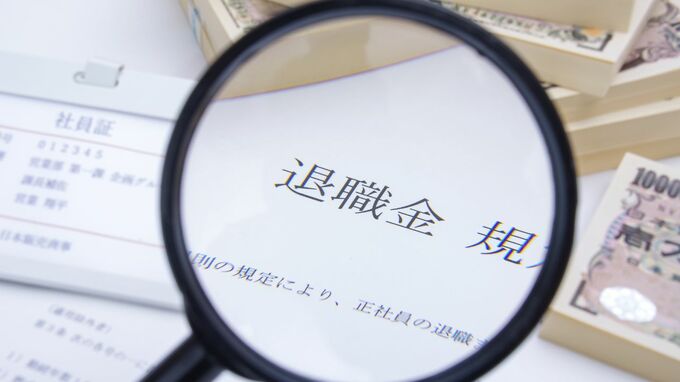退職金を「家族に分散」するとさらに節税できる
経費として認められるのは、社長本人だけではありません。家族従業員への支給も認められています。家族従業員にも退職金を分散すれば、社長1人だけで全額受け取るよりも、累進税率の適用が抑えられ、節税につながることがあります。それに加えて、先ほど説明した退職所得の計算が適用されるので、税額が安く算出されます。これは、会社にした場合の大きなメリットといえます。
事業が軌道に乗ってくると、順調に利益が増えて、いろいろな節税策を施します。その間、「経営セーフティ共済(次の項目参照)」や各種の生命保険などを利用すれば、潤沢なお金が外部に残ります。
しかし、問題なのはそれを解約する時期です。その際には、解約金を受け取る会社側は臨時収入となるので、利益が増えてしまい、余分な法人税が発生するおそれが出てきます。
そこで、会社をつくった場合に、事前に計画しておきたいのが、家族従業員の退職時期です。給料と同じで1人ひとりに与えられる「退職所得控除」という権利を十分に活用しましょう。
それには、事前に生命保険の満期やその解約時期を、退職時期にあわせておくことをオススメします。そうすれば、解約金という会社の「収益」を、退職金という会社の「経費」で相殺できて、必要以上に高い税金を支払わなくて済みます。
「個人事業の退職金」はNG
ここまで説明してきたように、退職金は節税メリットが大きいのですが、じつはこの考え方は個人事業に対しては認められていません。「個人事業主が、個人事業主自身に対して支払う退職金」という考え方自体がありえないからです。
また、長年ともに頑張って働いてきた家族専従者への退職金も、経費として認められていません。
個人事業主にとって、仕事を辞めたあとに生活費をどうやりくりするかは大きな問題です。個人事業主のほとんどは国民年金のみに加入していますが、現状では国民年金を満額支払われても、年間80万円程度の額しか受け取れません。
また、老後のために資金を備える手段を生命保険に頼ろうとしても、支払った保険料は事業の経費として認められません。しかも、認められている所得に対する生命保険料控除は最高でも12万円でしかありません。
今のやりくりも大切ですが、将来の生活資金をどうするかは、もっと切実な問題です。そこで、「小規模企業共済」(掛金全額を経費算入できる)や「iDeCo」(掛金全額について所得控除を受けられる)といった、税負担を抑えながら効率よく老後資金を積み立てられる制度の利用が考えられます。
関根 俊輔
税理士法人ゼニックス・コンサルティング
税理士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】