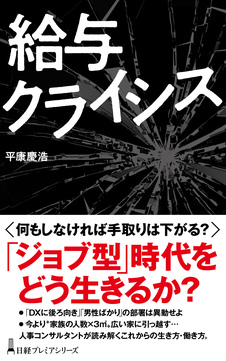「メンバーシップ型雇用」を支えたのは組合の給与交渉
しかし、メンバーシップ型には大きなメリットがある。そのことについてあらためて理解しておかなければ、これからの働き方や雇用がどう移り変わるのかは理解しづらい。
そもそも、日本において古来からメンバーシップ型の雇用が存在していたわけではない。
明治維新以降に資本主義が広がる中、雇用の仕組みは当然のごとく職務(ジョブ)型だった。職務の定義をしたうえで雇用をするのは当然だったのだ。
しかし戦時中の賃金統制令に基づく最低生活保障型を経て、戦後復興期にメンバーシップ型雇用が形成されていく。結果として、経営側に異動や転勤、長時間労働などの指揮命令権を与えていると解釈されるが、給与の観点から見た場合、年功的生活給が軸にあることを忘れてはならない。
そしてこの年功的生活給を誰が求めてきたのか、ということだ。
それは労働者自身であり、1980年代まで強い影響力を持っていた労働組合に他ならない。
戦後間もない時期から1980年代までは春闘でベースアップが議論され、5月1日は労働者の祭典としてメーデーが各地で開催されていた。組合は多くの労働者を組織化し、労働者の代表として生活給の引き上げを主張し続けた。そして経営者側も組合と協調しながら、対話によって利益配分を推し進めていった。
つまり1980年代までの男性中心、年功主義を軸とした給与の仕組みは、生活給としての水準を経営層と労働組合との交渉によって担保していたのだ。
一方、昨今議論になる職務(ジョブ)型の雇用では、給与は原則として市場原理によって決定することになる。この違いを踏まえて、メンバーシップ型雇用を理解しなくてはならない。
そもそも世界的な歴史を踏まえると、雇用と給与決定の歴史は、まず交渉(トレード)型から始まっている。一定の技術を持ったギルド集団が自らの賃金を団体として交渉し、受け取る権利を獲得していたという。
日本における労使関係も、生活給という概念をベースにしている点で違いはあれども、経営層と労働者側の団体とが交渉し、昇給額や一時金としての賞与額を決定する仕組みは、まさにコレクティブ・バーゲニング(集合取引…のちに団体交渉と訳されるようになる)である。
一方で最近よく目にする職務(ジョブ)型という雇用形態は、その後のあまたの変遷を経たのち、1900年代初頭にアメリカでフレデリック・テイラーにより科学的管理手法として明文化されたものを指す。そこでの給与決定における特徴は生産性概念だったが、1940年代以降にエドワード・ヘイによって広められた職務評価によって、市場概念を持つようになる。
それは1960年代以降急速に世界に広がるが、新自由主義的な市場原理がその根底にあることを忘れてはいけない。
コロナショックを経た今の私たちが職務(ジョブ)型として理解している雇用と給与決定の仕組みは、職務の価値を市場取引によって決定しようとする仕組みだ。つまり1990年頃まで日本で主流だった、労使関係の交渉(トレード)による雇用と給与決定の仕組みが、市場価値(マーケット)に基づく雇用と給与決定の仕組みに変わるものとして理解しなくてはならない。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】