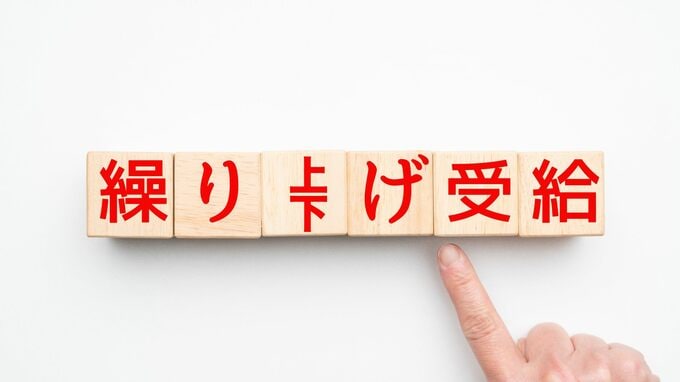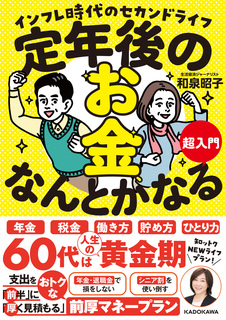繰り下げみなし増額制度導入に込められたメッセージ
さて、今回の制度変更には、どんなメッセージが込められているでしょうか。
未来の予測が不可能だとすると、年金について、「トータルでいくら受け取れるか」という損益分岐点で考えること自体が、あまり生産的ではないといえます。
そこで、公的年金制度の根本の趣旨に立ち返って考えてみる必要があります。
公的年金制度は「長生きリスクに備える保険」として設計されたものです。だからこそ、私たちが納めるお金も「保険料」といわれているのです。貯蓄とは異なります。だからこそ、若い世代が高齢者の分を負担している特殊なしくみがとられているということです。
この分野の第一人者である日本年金学会幹事の谷内陽一氏の有名な格言に、「繰り下げて後悔するのはあの世、繰り上げて後悔するのはこの世」というのがあります。これがまさに正鵠を射ているといえます。
繰り上げ受給して、80歳より長生きしてしまった場合、トータルでの受給額は減ります。しかも、80歳以降については減額された低い受給額をずっと受給し続けることになります。
これに対し、繰り下げ受給をすれば、年金の額が最大で84%増え、長生きした場合にお金が足りなくなるという事態が起こりにくくなります。
また、高度成長期と今とでは、状況がまるで違います。日本経済の勢いも、人口構成も、大きく異なります。
高度成長期は、日本経済が好調なのに加え、高齢者よりも若年層の方が圧倒的に多かったのです。しかも、平均寿命も今よりは短かったので、老後資金の心配はそれほど必要ありませんでした。
しかし、現在は高齢化、少子化が進行しており、今後さらに進むことが予測されています。
寿命が延びて老後が長くなっていけば、老後資金をその分、多く賄わなければなりません。
他方で、現実に少子化が進行するなか、若い世代に過大な負担を負わせないように工夫する必要があります。
そのなかで、「繰り下げみなし受給」の制度は、公的年金制度をできる限り長く維持するための、有効な選択肢の一つといえるのではないでしょうか。
とはいえ、公的年金は、国民の老後の生活を保障するための根幹です。
最近、国はiDeCoやNISAといった、自己責任による投資をうながす「私的年金」の制度を充実させています。これはけっこうなことであり、重要なことであるといえます。しかし、その比重を大きくしていくことが、公的年金をはじめとする社会保障に対する国の責任放棄につながることになってしまわないよう、国民の立場からは、チェック機能を働かせていく必要があります。
\1月10日(土)-12日(月)限定配信/
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【1/7開催】
高市政権、トランプ2.0、日銀政策、AIバブル…
2026年「日本経済と株式市場」の展望
【1/8開催】地主の資産防衛戦略
「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…
権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術
【1/8開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
【1/10-12開催】
「タックスヘイブン」を使って
節税・秘匿性確保はできるのか?
「海外法人」の設立法・活用法
【1/10-12開催】
遺言はどう書く?どう読む?
弁護士が解説する「遺言」セミナー<実務編>