【事例3】遺言書により自宅売却で得たお金の寄付を指示
【登場人物】
- Aさん:身寄りのない80代の男性
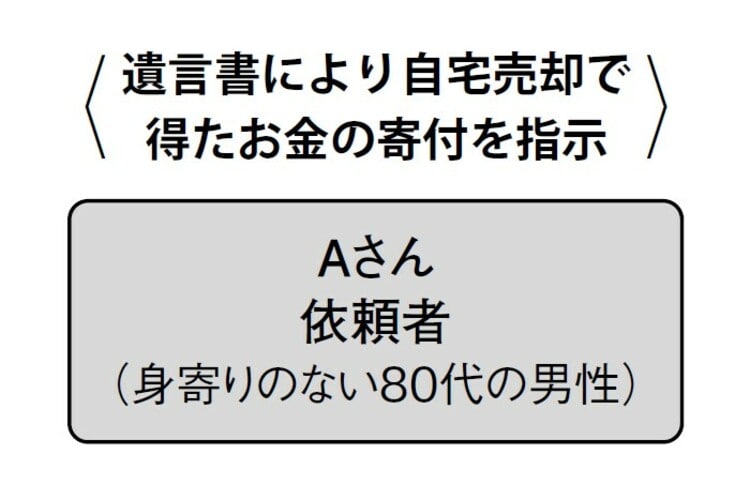
Aさんは、定年を迎えるまで40年以上小学校の教師をしていました。結婚歴はなく子どもはいません。遠方に兄弟がいましたが亡くなってしまい、甥と姪(法定相続人)が5人ほどいるようですが50年以上音信不通です。
Aさんは自宅不動産だけでなく、賃貸不動産をもちその収入で生活していました。しかし、自分が死亡したあとはそれらを知らない甥や姪に相続させるのではなく、売却して奨学金の基金へ寄付したいと思っていました。
そこで不動産業者に相談することにしました。
本人の死後、相続人ではない人や団体に寄付することを遺贈といいます。その不動産業者にとって遺贈は、当然ながら専門外。すぐに知り合いの弁護士に協業を依頼しました。
このケースでも清算型の遺言を利用することにしました。死後に所有する不動産を売却し、そこで得たお金で入院費や葬儀などの支払いを済ませたうえで残りを寄付(遺贈)するという遺言書を残したのです。
ここで重要なのが遺言執行者の存在です。遺産を遺贈する場合の不動産登記は、遺言執行者が行うことになるので、遺言書で遺言執行者を指定しておくことが必須となります。
また、不動産業者としては、遺言によって死後の不動産売却を依頼されても、相続人の居所が分からない場合は手続きが困難となります。そのため、このような清算型の遺言書で遺言執行者を指定しておくことは、不動産業者にとっても必須事項になるはずです。
それだけでなく、Aさんが債務(最期にいた施設や病院の費用、固定資産税などなんらかの負債があるはずです)を負っている場合、これらが法定相続人に向いてしまう可能性もあるので、トラブルを避けるために遺言執行者の権限としてAさんの負債を弁済することも含んでおくべきです。こうしておくと葬儀費用の支払いも遺言執行者が行うことができます。
【事例3】では、弁護士と協業経験のある司法書士が遺言執行者になりました。そして遺言執行者がAさんの死後にAさんが相談した不動産業者の仲介により不動産を売却し、売却金から入院費用や葬儀費用そのほか経費を支払ったあとに残金を奨学金の基金(受遺者)へ寄付しました。つまり、Aさんの希望はすべてかなったわけです。



























