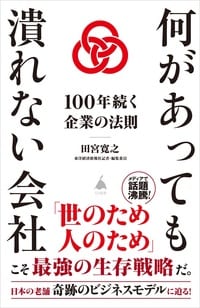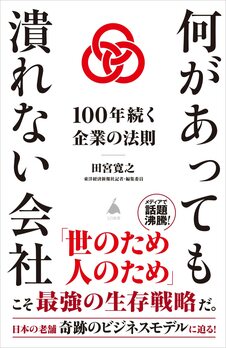石油製品の需要が減る中、タツノが見据える「未来」
ガソリン、ジェット燃料、灯油、軽油など石油製品の需要は年々減少傾向にある。
経済産業省の試算によると、2021~2025年の石油需要は年平均マイナス1.5%、5年間の合計でマイナス5.7%になる見込みだ。長年、石油製品を扱って栄えてきた企業も、今後、石油に加えさまざまな新エネルギーを取り扱うことで、これまで通り社会に貢献していかなければならない。
焦眉の急は新エネルギーへの取り組みだ。燃料の元売り企業も自動車メーカーも、こぞってガソリン一辺倒からの脱却を試みている。ガソリン計量機メーカーであるタツノも、そんな時代の変化と無縁ではいられないが、実はとっくに次の一手を打っていた。
1996年(平成8)に開発に着手し、完成させた水素ディスペンサーは、現在、国内と北米で50%強のトップシェアを確保しているのだ。トヨタ自動車が、水素を燃料とするFCV(燃料電池車)の開発に本格的に取り組み始めたのは1992年(平成4)のこと。その動向を横目に見ながら、タツノも水素事業を発足させたことになる。
また、CNG(圧縮天然ガス)やLNG(液化天然ガス)の充塡機もすでに製品化されている。次は、いよいよ電気自動車(EV)事業への参画を検討しているようだ。新エネルギー時代の到来を睨み、積極的に投資を行う考えだ。
ただし、いくら新エネルギーが求められているからといっても、タツノは、ガソリン計量機がなくなるという未来は描いていない。タツノが見据えているのは、旧来のガソリンスタンドから発展した「次世代サービスステーション」だ。
根底にあるのは、ガソリンを旧エネルギーとして切り捨てるのではなく、使い勝手を進化させることで、新エネルギーと肩を並べられるようにするという発想だ。その一環として完成させたのが、ガソリン給油時に発生するベーパー(ガソリンが空気に触れてわずかに蒸発した気体)をガソリンとして再利用する「エコステージ」である。
ガソリンスタンドで給油時に特有の臭いがするのは、ベーパーとなり、大気中に飛散しているからだ。臭いが不快であるだけでなく、火気に触れれば爆発する危険物でもある。
タツノの「エコステージ」とは、ベーパーが大気中に飛散する前に給油ノズルから吸引、冷却して液体化し、給油ラインに戻すという機能を兼ね備えたガソリン計量機だ。ここまで読んで、そういえば最近のガソリンスタンドはガソリンの臭いがしないと気づいた人も多いだろう。
このようにガソリンという燃料の安全性と効率性を高める。そしてガソリン車だけでなく、車種に合わせて水素やCNG、LNGの充塡も、電気自動車の充電も可能な総合燃料充塡施設というのが、タツノのビジョンにある「次世代サービスステーション」なのである。
ガソリンスタンドの数は、ピーク時の1990年代半ばには約6万軒だったものが、現在では約3万軒と半減している。スタンドが減れば、当然、売れる計量機も減ってしまう。
やはり今までと同じことをしていたのでは、スタンド施工への投資を呼び込めず、経営が苦しくなってしまうという危機感は強くなっているという。新しいことにチャレンジする気運は社内でいっそう高まっている。
すでに成功しているチャレンジの筆頭は、先に触れた水素ディスペンサーだ。業界最新鋭との自負がある。ただし、水素自動車が世界に普及するにはまだまだ時間がかかりそうだ。
水素社会が実現するのは、いつになるか。10年後か20年後か、それまでは「歯を食いしばって水素ビジネスに取り組む」と能登谷常務は話すが、タツノには「次世代サービスステーション」を燃料業界のスタンダートとしていくという確固たるビジョンがある。
約110年、「給油」にまつわる新しいものを数々、世に送り出してきたタツノのチャレンジが止まることはない。
<何があっても潰れない会社の極意>
●「正確性」「性能の持続性」という量り売りの基本を守り通し、信頼を積み重ねた
●受け継がれてきた技術を時代の要請に応じて改良し、常に新しいものづくりを実行した
●顧客ニーズを熟知する営業が、現場の声を吸い上げて新商品を考案
田宮 寛之
経済ジャーナリスト
東洋経済新報社 記者、編集委員
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】