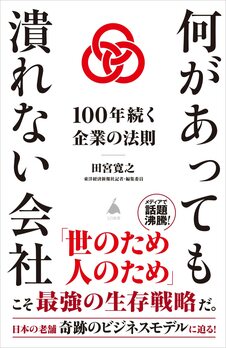特許、実用新案、意匠の出願件数は5000件以上
初代・龍野右忠が日本初のガソリン計量機を作ったことに始まり、タツノは常に新しいものの研究開発に力を注いできた。
たとえばガソリンPOSシステム(販売時点情報管理)だ。
昔のガソリンスタンドでは、客の自動車に給油したサービスマンが事務所のスタッフに給油量を伝える→事務所スタッフが伝票を作成する→サービスマンが事務所へ走り、伝票を受け取って客のもとへ戻り、支払いを受ける、という順序で給油業務が行われていた。
しかし口頭連絡ではミスが起こりやすい。事務所スタッフが聞き違えたり、サービスマンが伝え間違えたり、はたまた忙しすぎて給油量を忘れてしまうこともある。こうして多発する伝票の付け落ちで帳簿が合わなくなるというのは、ガソリンスタンド経営者にとって長年の悩みの種だった。
それを解消すべく、1970年(昭和45)にタツノが完成させたのが、計量機と連動して伝票を自動発行する業界初のガソリンPOS「パンチライターシステム」だ。これにより伝票記入の必要がなくなり、作業効率アップ、人件費削減というメリットがガソリンスタンドにもたらされた。今では当たり前のことだが、当時は画期的だったのだ。
もう1つ一般人にもわかるものを挙げると、敷地が狭いガソリンスタンドでよく目にする「懸垂式ガソリン計量機」だ。天井から吊り下げるタイプのこの計量機は、タツノの特許製品である。消防法上、強く難色を示されたところを安全性などを解決し、実用化と特許獲得にこぎつけたのは2代目の龍野日吉だった。
その他、「セルフ給油所での精算システム」や「セルフ給油所での給油管理システム」「遠隔監視システム」、さらにはタンクローリーの油種情報を管理することでコンタミ事故(貯蔵している油種とは違うものを注入してしまう事故)を防止する「ハイテクローリーシステム」など、タツノの特許、実用新案、意匠の出願件数は5000件以上におよぶ。
「日本に、世界に、まだ存在しないものを作りたい」
では、すでに揺るぎない業界内地位を確立しているタツノが現状に甘んじず、絶えず新しいものを追い求めているのはなぜなのか。
その理由として考えられるのが、創業以来、受け継がれている「新しいもの好き精神」と「失敗を許容する寛容性」の2点だ。
日本で最初のガソリン計量機を完成させた初代、世界で最初の懸垂式ガソリン計量機を完成させた2代目、そこに見られる「日本に、世界に、まだ存在しないものを作りたい」という精神が、今の社員にも浸透しているという。
また、企業の存続には環境順応性が欠かせない。
「100年、200年と続いている企業はどこも、すでに完成された技術をそのまま使って今に至っているわけではなく、そのときどきの環境に順応してきたはず」(能登谷常務)
創業から111年間、戦争や天災に加え、さまざまな社会環境の変化に対応してチャレンジを積み重ねてきた。タツノにとって「常に新しいことを探究する」というのは特別でも何でもない、当たり前のことだという。
膨大な特許を可能にした成功例の影には、失敗例も数多くあるそうだ。たとえば洗車機の開発を試みた際には、さまざまな不具合が発生し、開発自体を見直したという。
企業の存続を危機にさらすような致命的な失敗は避けねばならないが、基本的には失敗を糧としてさらに進化するというのがタツノの社風だ。だからこそ、多くの成功例も生まれ、今があるというわけだ。
このように新規事業に積極的と聞くと、さぞかし企画事業部は活気にあふれているだろうと想像されるが、タツノには特に企画立案を担当する部署はないという。では誰が新製品の企画を立てるのかというと、営業の社員たちだ。
タツノでは、「製品を売る部署」と「売れた後の現場管理をする部署」が分かれておらず、営業の社員が販売から現場管理まで一括して担っている。つまり、営業の社員は日常的にガソリンスタンドを回り、現場のニーズをもっとも察知しやすい位置にいる。彼らにとって、現場の声を吸い上げて新製品を考案するというのは、ごく自然なことなのである。
加えて、長い歴史のなかで築いてきた顧客との信頼関係により、営業の社員には幅広い情報が入ってくるというのも大きい。顧客から入手したレア情報が、新製品に反映されることもよくあるそうだ。
タツノには、祖父から父、父から子へと、何世代にもわたって取引してきた顧客も多い。世代を超えて信頼関係を築いてきた顧客は、もはや客というよりも、より良い製品を一緒に模索する「パートナー」と呼んだほうがしっくりくるという。